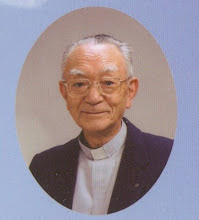朗読聖書: Ⅰ. 創世記 18: 1~10a. Ⅱ. コロサイ 1: 24~28.
Ⅲ. ルカ福音書 10: 38~42.
① 新約聖書が書かれた時代のローマ史、特にオリエント諸地方の社会的状況を細かく調べてみますと、それはある意味で現代世界・現代社会を先取りした一つの雛形のような印象を受けます。それまでの各国、各民族・部族毎の伝統的文化や慣習、価値観などは、シルクロードの開発や各種の発明などで急速に広まって来た国際的経済交流や文化交流により、時代遅れのものと見做されたり、軽視されたりするようになり、多くの若者たち、特に能力ある者たちは、積極的に新しい技術や、新しい商品・文化・価値観などを捜し求め、新しい流行、新しい流れの中で生活しようと努めていたように思われます。
② このことは、新約聖書の中にもいろいろな形で反映しています。例えば本日の福音の少し後のルカ福音12章には、明日の食事のことで思い煩う無産者たちに、主が父なる神の摂理に対する信頼心を強調したり、盗人がいつ来るか分らないので腰に帯をしめ、目を覚ましているようにと警告したり、忠実な僕と不忠実な僕の譬え話をしたり、「今から後、一家に5人の者がいるなら、三人は二人に、二人は三人に対立して分かれる。父は子に、子は父に、母は娘に、娘は母に、姑は嫁に、嫁は姑に対立して分かれるであろう」などと話したりしておられます。これらのことは、現代社会にも到る所で頻発している現象ではないでしょうか。もう長年来の伝統的社会秩序がよく守られているような落ち着いた時代ではないのです。同じ家に生まれ育った兄弟姉妹であっても、性格も好みも価値観も大きく異なっていることが珍しくありません。親子であっても同様です。ですから、主が話された「放蕩息子の譬え話」にある親子の考えの違いや、兄弟の考えや性格の違いなどは、現実にも大いにあり得たことだと思います。現代社会においても同様ではないでしょうか。
③ 本日の福音も、このような大きな社会的過渡期の流れの中で、受け止めたいと思います。主が弟子たちを連れてやって来た村は、エルサレムに近いベタニヤという村でした。そこにはラザロという、多分富裕な貿易商と思われる人が大きな家屋敷を構えていて、いつも主の一行を快く泊めてくれていました。主のご受難の少し前に、このラザロが死んで屋敷内の墓に葬られていたのを、主が蘇らせた話がヨハネ11章に書かれていますが、そこにもマルタとマリアの姉妹が登場しています。福音書には、罪の女マグダラのマリアもいて、主によってその心の罪から救われたこの女が、主の受難死と復活の時にも主に忠実に留まり続けて活躍したように描かれていますが、同じ古代末期の崩れ行く社会の中に生まれ育ち、4世紀後半に長年エルサレムにあって新約聖書をラテン語に翻訳したり、聖書の注解書を著したりした聖ヒエロニモは、このマグダラのマリアとラザロの妹マリアとを、同一人物としています。しかし、社会体制も社会道徳も比較的安定していた時代しか知らないある聖書学者が、この二人が同一人物であるとは考えられないという仮説を唱えたことがありました。確かに、首都圏の立派な資産家の家に生まれ育った女が、貧しい家の出身者が多い遊女の間に生活する程に身を持ち崩し、社会からも「罪の女」として後ろ指を指されるに到ったなどということは、通常には考えられないことですが、しかし、社会全体が根底から文化的液状化現象で揺らぎ、社会道徳も心の教育も、基盤とする権威を失って崩壊しつつあるような時代には、現代においても起こり得るのではないでしょうか。良家の娘が家出をしたりした話は、現代にもたくさんありますから。
④ 本日の福音に戻りますと、罪の女の生活から足を洗って元の家に戻っている、そのマリアがいる家に主が弟子たちを連れてやって来ました。妹と違って伝統的良風を堅持し、家事を任せられていたと思われるマルタは、突然の客たちの夕食の準備で大忙しであったと思われます。ルカ福音書8章の始めには、「悪霊や病気から救われた数名の婦人たち、すなわち七つの悪魔を追い出してもらったマグダラのマリアと、ヘロデの家令クーザの妻ヨハンナ、それにスザンナ」たちも主と弟子たちの一行の「お供をした。彼女たちは、自分たちの財産を出し合って一同に奉仕していた」とありますから、この時も数人の婦人たちがマルタのお手伝いをしていて、マルタは決して一人で食事や宿泊の準備をしていた訳ではないと思われます。マルタという名前は、当時シリア、パレスチナ地方に住んでいた庶民、異教徒もユダヤ人もごく一般的に話していたアラム語で「女主人」の意味だそうですが、家のことは自分が一番よく知っているのですから、マルタは名実共に女主人として、本日の福音の40節にありますように、「いろいろのもてなしのため、せわしく立ち働いていた」のだと思います。せわしく立ち働く(ペリスパオー)というギリシャ語原文の動詞は、ペリ(周囲に)とスパオー(引き離す)という二つの単語の合成語ですから、マルタは、他所から来た婦人たちにいろいろと指示を与えながら、周囲の雑事に囚われて、心が散り散りになっていたのかも知れません。
⑤ ところが、自分の家のことをよく知る妹のマリアは婦人たちと一緒に手伝おうとせず、広間で主の弟子たちと一緒に、主の足元に座して、主の話を聞き入っていました。当時の伝統的慣習では、女性は公的なシナゴガだけではなく、個人宅の広間などでも客人の男性たちの間に一人で入り混じって話を聞いたり論じ合ったりすることは、慎みに欠ける行為とされていました。当時の律法学者たちが、律法の教えを学ぶことは男の務めであって、女性にはふさわしくないと教えていたからでもあると思います。伝統的慎みの慣習を重視していたと思われるマルタは、折角自宅に戻って来た妹のそのような慎みを欠く行為を見て、できれば一言すぐに注意したかったでしょうが、主のすぐ真ん前ですし、主が何もおっしゃらないので、暫くは見て見ぬふりをしていたのかも知れません。しかし、遂に我慢できなくなったのだと思います。主のお側に近寄って「主よ、妹が私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃって下さい」と申しました。
⑥ 主はそれに対して「マルタ、マルタ」と二度も名前を呼んでいますが、これはマルタへの親しみの情の表現だと思います。「あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである」というお言葉は、今の私たちにとっても忘れてならないお言葉だと思います。私たちも、神に捧げる祈りや典礼のことで、間違わないようにいろいろと細かく配慮しますし、客人のもてなしや隣人との人間関係のためにも、人から良く思われるようにと種々配慮しています。その配慮は必要でありますが、しかし、そのことで心を乱し、客人に対する接待を喜びの心のこもらないものにしてはならないというのが、主の教えではないでしょうか。外的この世的配慮の価値は、それらの配慮や奉仕に込める神や客人への感謝と愛にあると思います。人と人の考えや好みや価値観などが大きく多様化するような時代には、この本質を念頭において、外的この世的不完全さに心を乱さずに、ひたすら神の方に眼を向けて、喜んでなす奉仕愛に生きるように、というのが主のお勧めなのではないでしょうか。
⑦ 最後に「マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない」というお言葉も、大切だと思います。ここで「良い方」とある言葉は、何を指しているのでしょうか。いろいろと意見があるでしょうが、私はこれを、昔ある人たちが考えたような観想生活のことではなく、自分に対する主の御言葉、神からの呼びかけなどを指していると思います。罪から立ち上がる恵みを得たマリアは、ひたすら神よりの呼びかけにのみ心を向けて生きようとしていたのではないでしょうか。女性を家事や子育てだけに閉じ込めて来た旧来の伝統に反対し、いわば自分も主の女弟子になって、男たちと共に主のお言葉を聴聞し、その証し人になることを望んでいたのかも知れません。主はその大胆な試みを快く容認なされ、そのことを「良い方」と表現なされたのかも知れません。この世の伝統的やり方や考え方を最高の基準とせず、その人が神を愛し神に従おうとしているなら、その人のそのような心がけを是とし、多少の不完全があるとしても心を大きく開いて容認致しましょう。それが、人間がそれぞれ極度に多様化する大きな過渡期に、主が多種多様な個性的人々を救うためにお示しになった生き方だと思います。現代もそのような大きな過渡期と言ってよいと思います。私たちも主のそのような心の広い生き方を身につけるよう心がけましょう。
2010年7月18日日曜日
2010年7月11日日曜日
説教集C年: 2007年7月15日 (日)、2007年間第15主日(三ケ日)
朗読聖書: Ⅰ. 申命記 30: 10~14. Ⅱ. コロサイ 1: 15~20.
Ⅲ. ルカ福音書 10: 25~37.
① 本日の第一朗読の中で、モーセは「あなたの神、主の御声に従って、…あなたの神、主に立ち帰りなさい」と言った後に、「この戒めは難し過ぎるものでもなく、遠く及ばぬものでもない。…御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる」と話しています。長年待望して来た約束の地を目前にして、モーセの語ったこの言葉は、私たちの信じている神をどこか遠い海の彼方や、天高くに離れておられる方と考えないように、神はいつも私たちのごく近くに、ある意味では私たち自身の頭の考えよりも私たちの心の近くにおられて、私たちの話す言葉や私たちの心の思いの中でまでも働いて下さる方なのだ、と強調しているのではないでしょうか。察するに、モーセは自分の口や心の中での神のそのような神秘な働きを実際に幾度も体験し、神の身近な現存を確信していたのだと思われます。私たちも神のこの身近な臨在に対する信仰を新たにしながら、その神のひそかな御声に心の耳を傾け、神の働きに導かれて生活するよう心がけましょう。それが、私たちの本当の幸せに到達する道であると信じます。
② 本日の福音には、一人の律法の専門家が主に「永遠の命をいただくには、何をしなければなりませんか」と尋ねていますが、当時の律法学者たちは、旧約聖書に書かれている数多くの法や掟を、私たちの言行を律する外的理知的な法規のように受け止め、人間の力ではそれらを全部忠実に守り尽くすことはできないので、それらの内のどの法、どの掟を守ったら永遠の命をいただいて幸せになれるかを論じ合っていたようです。この律法学者も、その答えを主に尋ねたのだと思います。主が「律法には何と書いてあるか。あなたはそれをどう読んでいるか」とお尋ねになると、その人はすぐ「心を尽くし精神を尽くし、云々」と、申命記6章に読まれる愛の掟を口にしました。この掟は、今でもユダヤ教の安息日の儀式の中ほどに、声を大にして唱えられている、特別に重要視されている掟であります。ですから、その人の口からもすぐこの掟がほとばしり出たのでしょう。主は、「正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる」とお答えになりました。しかしその人は、毎週幾度も口にしているこの掟の本当の意味内容を理解できずにいたようで、実行と言われても、何をどう実行したら良いのか判らず、「では、私の隣人とは誰ですか」と、まず隣人について主に尋ねました。主がそれに答えて話されたのが、「善きサマリア人の譬え」と言われる話であります。
③ ある人がエルサレムからエリコへ下って行く、石と岩ばかりが累々と10数キロも続く長い淋しい荒れ野の坂道で、追いはぎに襲われて衣服まで奪い取られ、半殺しにされてしまいました。そこに一人の祭司が、エルサレムでの一週間の務めを終えて帰る途中なのか、通りかかりました。しかし、その人を見ると、道の反対側の方を通って行ってしまいました。聖なるエルサレム神殿での聖なる勤めにだけ奉仕していて、穢れたものや血の穢れのあるものには関わりたくない、という心が強かったのかも知れません。同じように、神殿に奉仕しているまだ若いレビ人も通りかかりましたが、その人を見ると、道の反対側を通って過ぎ去って行きました。日頃綺麗な仕事にだけたずさわっていることの多い私たち修道者も、神の導きで全く思いがけずに助けを必要としている人に出遭ったら、その人を避けて過ぎ去ることのないよう、日頃から自分の心に言い聞かせていましょう。
④ 1962年の夏、私が夏期休暇でドイツのある修道院に滞在した時、その近くにあったアメリカ軍のバウムホルダーという、人口3万人程の大きなキャンプ場からの依頼で、そのキャンプのホテルに二週間滞在し、アメリカ人と結婚している日本人女性数人に洗礼前の教理を教えたことがありました。日曜日のミサに出席しましたら、ちょうど本日のこの福音が読まれ、その時の米軍チャプレンは説教の中で、信徒に具体的にわかり易く説明しようとしたのか、少し笑みを浮かべながら通り過ぎた祭司をユダヤ教の「神父」、レビ人を「神学生」と呼んでいました。現代のカトリック聖職者も気をつけていないと、苦しんでいる人や助けを必要としている人に対して、冷たく対応してしまうおそれがあるかと思います。皆生身の弱さを抱えている人間です。気をつけたいと思います。
⑤ 譬え話に戻りますと、最後にサマリア人の旅人、おそらく商用で旅行している人が来て、その傷ついた人を見ると、憐れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分の驢馬に乗せます。そして宿屋に連れて行って介抱します。ここでルカが書いている「見て、憐れに思い、近寄る」という三つの動詞の連続は、主がナインの寡婦の一人息子を蘇らせた奇跡の時にも登場しており、ルカが好んで使う一種の決まり文句のようも見えます。なお、「憐れに思う」という動詞は、新約聖書に12回使われていますが、主の譬え話の中で放蕩息子の父親や、僕に対する主人の行為として、また半殺しにされた人に対するサマリア人の行為として3回使われている以外は、新約聖書では全て主イエズスの行為、または神の行為としてのみ使われています。従って、譬え話にある放蕩息子の父親も僕の主人も、共に神を示しているように、この善いサマリア人の譬え話においても、サマリア人の中に愛の神が働いておられる、と考えてよいと思います。
⑥ 主はこの譬え話をなされた後で律法の専門家に、「この三人の中で、誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか」とお尋ねになります。そして律法学者が「その人に憐れみの業をなした人です」と答えると、「あなたも行って、同じようにしなさい」とおっしゃいました。ここで、律法の専門家の「私にとって隣人は誰ですか」という質問に戻ってみましょう。主が「あなたにとって隣人はこの人です」と具体的に隣人を示して下さっても、その人に対する愛が生ずるとは限りません。この人を愛するよう神から義務づけられていると思うと、人間の心は弱いもので、その人に対する愛よりも嫌気が生じて来たりします。ですから主は、外から法的理知的にその人の隣人を決めようとはなさいません。実は、愛が自分の隣人を産み出すのです。しかもその場合、相手が自分に対して隣人になるのではなく、その人を愛する自分が、相手に対して隣人になるのです。このようにして主体的積極的に隣人を産み出し、隣人愛を実践することが、律法学者が始めに尋ねた「永遠の命をいただく」道なのです。同じことは、夫婦の相互愛についても言うことができると思います。そのようにして隣人愛・夫婦愛に生きる人の中で、苦しんでいる人・助けを必要としている人を見て、憐れに思い、近寄って助けて下さる神が働くのであり、その人は、自分の内に働くこの神の愛を、数々の体験によってますます深く実感し、自分の心が奥底から清められ高められて、日々豊かに強くなって行くのを見ることでしょう。私たちがそのような幸せな神の愛の生き方を実践的に会得できるよう、照らしと導きの恵みを願い求めつつ、本日のミサ聖祭を献げましょう。
Ⅲ. ルカ福音書 10: 25~37.
① 本日の第一朗読の中で、モーセは「あなたの神、主の御声に従って、…あなたの神、主に立ち帰りなさい」と言った後に、「この戒めは難し過ぎるものでもなく、遠く及ばぬものでもない。…御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる」と話しています。長年待望して来た約束の地を目前にして、モーセの語ったこの言葉は、私たちの信じている神をどこか遠い海の彼方や、天高くに離れておられる方と考えないように、神はいつも私たちのごく近くに、ある意味では私たち自身の頭の考えよりも私たちの心の近くにおられて、私たちの話す言葉や私たちの心の思いの中でまでも働いて下さる方なのだ、と強調しているのではないでしょうか。察するに、モーセは自分の口や心の中での神のそのような神秘な働きを実際に幾度も体験し、神の身近な現存を確信していたのだと思われます。私たちも神のこの身近な臨在に対する信仰を新たにしながら、その神のひそかな御声に心の耳を傾け、神の働きに導かれて生活するよう心がけましょう。それが、私たちの本当の幸せに到達する道であると信じます。
② 本日の福音には、一人の律法の専門家が主に「永遠の命をいただくには、何をしなければなりませんか」と尋ねていますが、当時の律法学者たちは、旧約聖書に書かれている数多くの法や掟を、私たちの言行を律する外的理知的な法規のように受け止め、人間の力ではそれらを全部忠実に守り尽くすことはできないので、それらの内のどの法、どの掟を守ったら永遠の命をいただいて幸せになれるかを論じ合っていたようです。この律法学者も、その答えを主に尋ねたのだと思います。主が「律法には何と書いてあるか。あなたはそれをどう読んでいるか」とお尋ねになると、その人はすぐ「心を尽くし精神を尽くし、云々」と、申命記6章に読まれる愛の掟を口にしました。この掟は、今でもユダヤ教の安息日の儀式の中ほどに、声を大にして唱えられている、特別に重要視されている掟であります。ですから、その人の口からもすぐこの掟がほとばしり出たのでしょう。主は、「正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる」とお答えになりました。しかしその人は、毎週幾度も口にしているこの掟の本当の意味内容を理解できずにいたようで、実行と言われても、何をどう実行したら良いのか判らず、「では、私の隣人とは誰ですか」と、まず隣人について主に尋ねました。主がそれに答えて話されたのが、「善きサマリア人の譬え」と言われる話であります。
③ ある人がエルサレムからエリコへ下って行く、石と岩ばかりが累々と10数キロも続く長い淋しい荒れ野の坂道で、追いはぎに襲われて衣服まで奪い取られ、半殺しにされてしまいました。そこに一人の祭司が、エルサレムでの一週間の務めを終えて帰る途中なのか、通りかかりました。しかし、その人を見ると、道の反対側の方を通って行ってしまいました。聖なるエルサレム神殿での聖なる勤めにだけ奉仕していて、穢れたものや血の穢れのあるものには関わりたくない、という心が強かったのかも知れません。同じように、神殿に奉仕しているまだ若いレビ人も通りかかりましたが、その人を見ると、道の反対側を通って過ぎ去って行きました。日頃綺麗な仕事にだけたずさわっていることの多い私たち修道者も、神の導きで全く思いがけずに助けを必要としている人に出遭ったら、その人を避けて過ぎ去ることのないよう、日頃から自分の心に言い聞かせていましょう。
④ 1962年の夏、私が夏期休暇でドイツのある修道院に滞在した時、その近くにあったアメリカ軍のバウムホルダーという、人口3万人程の大きなキャンプ場からの依頼で、そのキャンプのホテルに二週間滞在し、アメリカ人と結婚している日本人女性数人に洗礼前の教理を教えたことがありました。日曜日のミサに出席しましたら、ちょうど本日のこの福音が読まれ、その時の米軍チャプレンは説教の中で、信徒に具体的にわかり易く説明しようとしたのか、少し笑みを浮かべながら通り過ぎた祭司をユダヤ教の「神父」、レビ人を「神学生」と呼んでいました。現代のカトリック聖職者も気をつけていないと、苦しんでいる人や助けを必要としている人に対して、冷たく対応してしまうおそれがあるかと思います。皆生身の弱さを抱えている人間です。気をつけたいと思います。
⑤ 譬え話に戻りますと、最後にサマリア人の旅人、おそらく商用で旅行している人が来て、その傷ついた人を見ると、憐れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分の驢馬に乗せます。そして宿屋に連れて行って介抱します。ここでルカが書いている「見て、憐れに思い、近寄る」という三つの動詞の連続は、主がナインの寡婦の一人息子を蘇らせた奇跡の時にも登場しており、ルカが好んで使う一種の決まり文句のようも見えます。なお、「憐れに思う」という動詞は、新約聖書に12回使われていますが、主の譬え話の中で放蕩息子の父親や、僕に対する主人の行為として、また半殺しにされた人に対するサマリア人の行為として3回使われている以外は、新約聖書では全て主イエズスの行為、または神の行為としてのみ使われています。従って、譬え話にある放蕩息子の父親も僕の主人も、共に神を示しているように、この善いサマリア人の譬え話においても、サマリア人の中に愛の神が働いておられる、と考えてよいと思います。
⑥ 主はこの譬え話をなされた後で律法の専門家に、「この三人の中で、誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか」とお尋ねになります。そして律法学者が「その人に憐れみの業をなした人です」と答えると、「あなたも行って、同じようにしなさい」とおっしゃいました。ここで、律法の専門家の「私にとって隣人は誰ですか」という質問に戻ってみましょう。主が「あなたにとって隣人はこの人です」と具体的に隣人を示して下さっても、その人に対する愛が生ずるとは限りません。この人を愛するよう神から義務づけられていると思うと、人間の心は弱いもので、その人に対する愛よりも嫌気が生じて来たりします。ですから主は、外から法的理知的にその人の隣人を決めようとはなさいません。実は、愛が自分の隣人を産み出すのです。しかもその場合、相手が自分に対して隣人になるのではなく、その人を愛する自分が、相手に対して隣人になるのです。このようにして主体的積極的に隣人を産み出し、隣人愛を実践することが、律法学者が始めに尋ねた「永遠の命をいただく」道なのです。同じことは、夫婦の相互愛についても言うことができると思います。そのようにして隣人愛・夫婦愛に生きる人の中で、苦しんでいる人・助けを必要としている人を見て、憐れに思い、近寄って助けて下さる神が働くのであり、その人は、自分の内に働くこの神の愛を、数々の体験によってますます深く実感し、自分の心が奥底から清められ高められて、日々豊かに強くなって行くのを見ることでしょう。私たちがそのような幸せな神の愛の生き方を実践的に会得できるよう、照らしと導きの恵みを願い求めつつ、本日のミサ聖祭を献げましょう。
2010年7月4日日曜日
説教集C年: 2007年7月8日 (日)、2007年間第14主日(三ケ日)
朗読聖書: Ⅰ. イザヤ 66: 10~14c. Ⅱ. ガラテヤ 6: 14~18.
Ⅲ. ルカ福音書 10: 1~12, 17~20.
① 本日の第一朗読は、イザヤ預言書の最後の章からの引用ですが、イザヤはここで、バビロン捕囚から解放されてエルサレムに帰国しても、祖国の再建を難しくする様々の困難に直面している民に向かって、喜んで神に従うよう励ましつつ、平和と慰め、繁栄と豊かさを約束して下さる神のお言葉を伝えているのだと思われます。48年前の1959年に、大きな明るい希望のうちに司祭に叙階された時の私は、ここに「エルサレムと共に喜び祝い、彼女のゆえに喜び躍れ」と言われている「エルサレム」を、勝手ながら救われる全人類と考えてみました。その頃の日本は既に敗戦後の暗い貧困状態から抜け出て、豊かな社会を築こうとして皆意欲的に働いているように見えましたし、戦後目覚しく復興した西ドイツでは、「経済的奇跡」という言葉が持て囃されていました。イザヤの預言には、ただ今ここで朗読されましたように「平和を大河のように、国々の栄えを洪水の流れのように」という言葉も読まれます。半世紀前からの世界の動きを振り返って見ますと、多発する数多くの不穏な動きにも拘らず、この預言はある意味で現代の多くの国でも実現していると考えてよいのではないでしょうか。
② しかし、2千年前のエルサレムがその繁栄の絶頂期に徹底的に破壊され、廃墟と化してしまったように、今文明の豊かさを謳歌している国々も、その繁栄を支えてくれている陰の力、神の働きに対する感謝と奉仕を蔑ろにし、神から離れて生きようとしていると、その繁栄の地盤が崩壊し、思わぬ液状化現象によって建物全体が根底から倒壊する恐れに、悩まされる時が来るのではないでしょうか。聖書の語る神からの警告に、心して深く学ぶよう努めたいものです。
③ 本日の第二朗読は、ガラテヤ書の結びの言葉といってよいですが、このガラテヤ書は、異邦人キリスト者も皆割礼を受けて、神から与えられた律法を順守しなければならないと説く、ユダヤ主義者の誤りを排除するために書かれた書簡であります。ガラテヤ書3章に述べられている教えによると、神がアブラハムとそのただ一人の子孫、すなわちキリストに約束なさった救いの恵みは、その430年後にできた律法に由来するものではなく、神の約束が律法によって反故にされたのでもありません。律法は、信仰によってキリストを受け入れるように導く養育係として、与えられたのです。しかし、今や信仰によってそのキリストと一致し、神の子となる時代が到来したのですから、私たちはもはや養育係の下にはおらず、律法を順守しなくてもよいのです。もはやユダヤ人とギリシャ人の区別も、奴隷と自由人の区別もなく、皆キリストにおいて一つとなって神の子の命に生き、神の約束なさった恵みを受け継ぐ者とされているのです。
④ 使徒パウロはこの観点から、私たちを人間中心の文化や思想や自力主義から解放してくれる、「主イエス・キリストの十字架のほかに、誇るものが決してあってはなりません」、「大切なのは、新しく創造されることです」などと、本日の朗読箇所で述べているのだと思います。「私は、イエスの焼印を身に受けているのです」という言葉は、焼印を押されて主人の持ち物とされ、主人の考え通りに働く古代の奴隷たちを連想させますが、使徒パウロは、それ程に全身全霊をあげて神の子イエスの内的奴隷となり、神中心に生きる「神の子」という新しい被造物に創造されることに打ち込んでいたのだと思われます。私たちも、この模範に倣うよう心がけましょう。
⑤ 本日の福音を書いたルカは、主が6章に選定された12使徒を村々へ神の国宣教のために派遣した話を、9章に記述しています。続く10章の始めにも、今度は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりの全ての町や村へ、二人ずつ先に派遣されたと書いています。そして神の国の到来を宣べ伝え、病人を癒すために派遣された使徒たちと同様に、この72人の弟子たちも喜んで戻って来て、各人の仕事の成果を主に報告しています。ルカ福音書にだけ読まれるこの72人の指名と派遣の話は、ルカが、使徒たちだけではなく、救いの恵みを受けた一般信徒も、主から派遣されて自分の持ち場で出会う人々に、神の国の到来を証することの大切さを重視していた証拠だと思います。宣教は、教会から宣教師として公式に選ばれ派遣されている人たちだけが為す活動ではありません。第二ヴァチカン公会議は、教会は本質的に宣教師的であり、信徒も皆キリストの普遍的祭司職に参与していると宣言していますが、その教会に所属しているメンバーは皆、それぞれの持ち場、それぞれの生活の場で主から宣教の使命を頂いていると考えているからだと思います。
⑥ では、どのようにしてその使命を果たしたらよいでしょうか。本日の福音からヒントを得て、ご一緒に考えてみましょう。主は72人を派遣するに当たり、まず収穫のために働き手を送って下さるよう、収穫の主(すなわち天の御父・神)に願いなさい、と命じておられます。商工業の急速な発達で社会がどれ程豊かになっても、その豊かさの陰で自分の心の弱さ、未熟さを痛感させられ、悩んでいる人や道を求めている人は非常に沢山います。自分の心の欲を統御できずに、もう止めたい止めたいと思いながらも止められずに、アルコールや麻薬やギャンブルなどの奴隷のようになり、知りつつ健康を害している人や、良心の呵責に苦しみつつ資金作りのため悪事を働いている人も少なくありません。私は30数年前に、中学時代に親しかった同郷の優秀な下級生で、クレーン車操作の技術などで建築業界で活躍していた人が、アルコール依存症で仕事ができなくなり、妻子にも逃げられて入退院を繰り返し、遂に死ぬまでの間、一年間程その世話を担当したことがありますが、その時、自分の心を持ち崩したそういう人たちは、バランスよく健康に暮らしている人たちの何倍も多く深刻に苦しんでいることを、思い知らされました。2千年前のキリスト時代と同様、現代にも心の救いを捜し求めている人、必要としている人は大勢いるのではないでしょうか。
⑦ ですから主は、「収穫は多いが、働き手が少ない」とおっしゃったのだと思います。ここで「収穫」とあるのは、心の救いを必要としている人や捜し求めている人たちを指していると考え、また「働き手」とあるのは、何かの社会的資格を取って働く人ではなく、自分が体験した神の働きや神による救いを、感謝と喜びの内に他の悩んでいる人、求めている人の心に語り伝えることのできる人を指している、と考えてもよいと思います。主は、神の国の到来を証しするそういう働き手が少ないと嘆き、一人でも多くそういう働き手が増えるよう、天の御父に祈ることをお命じになったのだと思います。まず神が働き、その神から派遣されて実践的に証しするのが宣教だと思います。
⑧ 次に主は、このような信徒の派遣を「狼の群れに小羊を送り込むようなものだ」とも話しておられます。この世の一般社会には個人的あるいは集団的エゴイズムの精神で生活している人が大半で、そのような人たちにはいくら真面目に証ししても正しく理解されず、逆にその人たちと同じように考え行動するよう、強引に引き込まれることも起こり得ます。特に自分が何か、その人たちに利用価値ありと思われるような物を持っている場合には。それで主は、「財布も袋も履物も持って行くな。途中で誰にも挨拶するな」などと、警告なさったのだと思われます。しかし、神から自分に与えられた生活の場に入ったら、まず「この家に平和があるように」と神に祈りなさい。もしそこに神の平和を受けるに相応しい心の人がいるなら、あなた方の願った平和はその人の心に留まり、恵みをもたらすでしょうが、もしいなくとも、その平和は無駄にはならず、あなた方の上に戻って来るのです、と主は教えておられるのだと思います。このようにして、人から注目されるような富も能力も何もなくても、自分の魂に宿る神の働き、自分の頂いた神の恵みを出会う人たちに実践的に証しして、やがて主ご自身がその人たちに受け入れられるよう地盤造りをするのが、信徒の宣教活動だと思います。
⑨ 最後にもう一つ、主が「二人ずつ遣わされた」という言葉にも注目しましょう。釈尊は、ご自分が会得した人生苦超克の道を、できるだけ多くの人に伝えさせるために、弟子たちに一人ずつで行くようお命じになったそうですが、主が二人ずつ派遣なされたのは、何かの個人的悟りや生き方を伝えるためではなく、何よりもその二人が各人の考えや性格の違いを超えて、神の愛のうちに一致して働く実践を世の人々に実証させるためだと思います。我なしの積極的博愛のある所に神が臨在し、働いて下さるのですから。信徒の宣教活動の本質は、このような神の愛を証しすることである、と申してもよいのではないでしょうか。
Ⅲ. ルカ福音書 10: 1~12, 17~20.
① 本日の第一朗読は、イザヤ預言書の最後の章からの引用ですが、イザヤはここで、バビロン捕囚から解放されてエルサレムに帰国しても、祖国の再建を難しくする様々の困難に直面している民に向かって、喜んで神に従うよう励ましつつ、平和と慰め、繁栄と豊かさを約束して下さる神のお言葉を伝えているのだと思われます。48年前の1959年に、大きな明るい希望のうちに司祭に叙階された時の私は、ここに「エルサレムと共に喜び祝い、彼女のゆえに喜び躍れ」と言われている「エルサレム」を、勝手ながら救われる全人類と考えてみました。その頃の日本は既に敗戦後の暗い貧困状態から抜け出て、豊かな社会を築こうとして皆意欲的に働いているように見えましたし、戦後目覚しく復興した西ドイツでは、「経済的奇跡」という言葉が持て囃されていました。イザヤの預言には、ただ今ここで朗読されましたように「平和を大河のように、国々の栄えを洪水の流れのように」という言葉も読まれます。半世紀前からの世界の動きを振り返って見ますと、多発する数多くの不穏な動きにも拘らず、この預言はある意味で現代の多くの国でも実現していると考えてよいのではないでしょうか。
② しかし、2千年前のエルサレムがその繁栄の絶頂期に徹底的に破壊され、廃墟と化してしまったように、今文明の豊かさを謳歌している国々も、その繁栄を支えてくれている陰の力、神の働きに対する感謝と奉仕を蔑ろにし、神から離れて生きようとしていると、その繁栄の地盤が崩壊し、思わぬ液状化現象によって建物全体が根底から倒壊する恐れに、悩まされる時が来るのではないでしょうか。聖書の語る神からの警告に、心して深く学ぶよう努めたいものです。
③ 本日の第二朗読は、ガラテヤ書の結びの言葉といってよいですが、このガラテヤ書は、異邦人キリスト者も皆割礼を受けて、神から与えられた律法を順守しなければならないと説く、ユダヤ主義者の誤りを排除するために書かれた書簡であります。ガラテヤ書3章に述べられている教えによると、神がアブラハムとそのただ一人の子孫、すなわちキリストに約束なさった救いの恵みは、その430年後にできた律法に由来するものではなく、神の約束が律法によって反故にされたのでもありません。律法は、信仰によってキリストを受け入れるように導く養育係として、与えられたのです。しかし、今や信仰によってそのキリストと一致し、神の子となる時代が到来したのですから、私たちはもはや養育係の下にはおらず、律法を順守しなくてもよいのです。もはやユダヤ人とギリシャ人の区別も、奴隷と自由人の区別もなく、皆キリストにおいて一つとなって神の子の命に生き、神の約束なさった恵みを受け継ぐ者とされているのです。
④ 使徒パウロはこの観点から、私たちを人間中心の文化や思想や自力主義から解放してくれる、「主イエス・キリストの十字架のほかに、誇るものが決してあってはなりません」、「大切なのは、新しく創造されることです」などと、本日の朗読箇所で述べているのだと思います。「私は、イエスの焼印を身に受けているのです」という言葉は、焼印を押されて主人の持ち物とされ、主人の考え通りに働く古代の奴隷たちを連想させますが、使徒パウロは、それ程に全身全霊をあげて神の子イエスの内的奴隷となり、神中心に生きる「神の子」という新しい被造物に創造されることに打ち込んでいたのだと思われます。私たちも、この模範に倣うよう心がけましょう。
⑤ 本日の福音を書いたルカは、主が6章に選定された12使徒を村々へ神の国宣教のために派遣した話を、9章に記述しています。続く10章の始めにも、今度は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりの全ての町や村へ、二人ずつ先に派遣されたと書いています。そして神の国の到来を宣べ伝え、病人を癒すために派遣された使徒たちと同様に、この72人の弟子たちも喜んで戻って来て、各人の仕事の成果を主に報告しています。ルカ福音書にだけ読まれるこの72人の指名と派遣の話は、ルカが、使徒たちだけではなく、救いの恵みを受けた一般信徒も、主から派遣されて自分の持ち場で出会う人々に、神の国の到来を証することの大切さを重視していた証拠だと思います。宣教は、教会から宣教師として公式に選ばれ派遣されている人たちだけが為す活動ではありません。第二ヴァチカン公会議は、教会は本質的に宣教師的であり、信徒も皆キリストの普遍的祭司職に参与していると宣言していますが、その教会に所属しているメンバーは皆、それぞれの持ち場、それぞれの生活の場で主から宣教の使命を頂いていると考えているからだと思います。
⑥ では、どのようにしてその使命を果たしたらよいでしょうか。本日の福音からヒントを得て、ご一緒に考えてみましょう。主は72人を派遣するに当たり、まず収穫のために働き手を送って下さるよう、収穫の主(すなわち天の御父・神)に願いなさい、と命じておられます。商工業の急速な発達で社会がどれ程豊かになっても、その豊かさの陰で自分の心の弱さ、未熟さを痛感させられ、悩んでいる人や道を求めている人は非常に沢山います。自分の心の欲を統御できずに、もう止めたい止めたいと思いながらも止められずに、アルコールや麻薬やギャンブルなどの奴隷のようになり、知りつつ健康を害している人や、良心の呵責に苦しみつつ資金作りのため悪事を働いている人も少なくありません。私は30数年前に、中学時代に親しかった同郷の優秀な下級生で、クレーン車操作の技術などで建築業界で活躍していた人が、アルコール依存症で仕事ができなくなり、妻子にも逃げられて入退院を繰り返し、遂に死ぬまでの間、一年間程その世話を担当したことがありますが、その時、自分の心を持ち崩したそういう人たちは、バランスよく健康に暮らしている人たちの何倍も多く深刻に苦しんでいることを、思い知らされました。2千年前のキリスト時代と同様、現代にも心の救いを捜し求めている人、必要としている人は大勢いるのではないでしょうか。
⑦ ですから主は、「収穫は多いが、働き手が少ない」とおっしゃったのだと思います。ここで「収穫」とあるのは、心の救いを必要としている人や捜し求めている人たちを指していると考え、また「働き手」とあるのは、何かの社会的資格を取って働く人ではなく、自分が体験した神の働きや神による救いを、感謝と喜びの内に他の悩んでいる人、求めている人の心に語り伝えることのできる人を指している、と考えてもよいと思います。主は、神の国の到来を証しするそういう働き手が少ないと嘆き、一人でも多くそういう働き手が増えるよう、天の御父に祈ることをお命じになったのだと思います。まず神が働き、その神から派遣されて実践的に証しするのが宣教だと思います。
⑧ 次に主は、このような信徒の派遣を「狼の群れに小羊を送り込むようなものだ」とも話しておられます。この世の一般社会には個人的あるいは集団的エゴイズムの精神で生活している人が大半で、そのような人たちにはいくら真面目に証ししても正しく理解されず、逆にその人たちと同じように考え行動するよう、強引に引き込まれることも起こり得ます。特に自分が何か、その人たちに利用価値ありと思われるような物を持っている場合には。それで主は、「財布も袋も履物も持って行くな。途中で誰にも挨拶するな」などと、警告なさったのだと思われます。しかし、神から自分に与えられた生活の場に入ったら、まず「この家に平和があるように」と神に祈りなさい。もしそこに神の平和を受けるに相応しい心の人がいるなら、あなた方の願った平和はその人の心に留まり、恵みをもたらすでしょうが、もしいなくとも、その平和は無駄にはならず、あなた方の上に戻って来るのです、と主は教えておられるのだと思います。このようにして、人から注目されるような富も能力も何もなくても、自分の魂に宿る神の働き、自分の頂いた神の恵みを出会う人たちに実践的に証しして、やがて主ご自身がその人たちに受け入れられるよう地盤造りをするのが、信徒の宣教活動だと思います。
⑨ 最後にもう一つ、主が「二人ずつ遣わされた」という言葉にも注目しましょう。釈尊は、ご自分が会得した人生苦超克の道を、できるだけ多くの人に伝えさせるために、弟子たちに一人ずつで行くようお命じになったそうですが、主が二人ずつ派遣なされたのは、何かの個人的悟りや生き方を伝えるためではなく、何よりもその二人が各人の考えや性格の違いを超えて、神の愛のうちに一致して働く実践を世の人々に実証させるためだと思います。我なしの積極的博愛のある所に神が臨在し、働いて下さるのですから。信徒の宣教活動の本質は、このような神の愛を証しすることである、と申してもよいのではないでしょうか。
2010年6月27日日曜日
説教集C年: 2007年7月1日 (日)、2007年間第13主日(三ケ日)
朗読聖書: Ⅰ. 列王記上 19: 16b, 19~21. Ⅱ. ガラテヤ 5: 1, 13~18. Ⅲ. ルカ福音書 9: 51~62.
① 本日の三つの朗読箇所に共通しているのは、主に従う者が身につけるべき特性と言ってよいかも知れません。第一朗読にはそれが明確には示されていませんが、少し自由な推察を働かせながら探ってみましょう。第一朗読は預言者エリシャの召命の話ですが、その頃神の預言者は、王妃イゼベルに命を狙われて神の山ホレブ(すなわちシナイ山) に逃れたエリヤ一人だけでした。しかし、その預言者エリヤが天に召される日も近づいていました。そこで神はエリヤに現われて、神の山からダマスコの荒れ野へと向かわせ、二人の男に油を注いでそれぞれアラムの王、イスラエルの王となし、エリシャにも油を注いで、エリヤの後を継ぐ預言者にすることを命じます。こうしてアラムでもイスラエルでも軍事的対立が始まって、預言者の活躍を必要とする舞台が生まれたのでした。
② 第一朗読は、エリヤがそのエリシャを預言者として召し出す独特の仕方について伝えています。言葉で呼びかけて自分に従わせたのではありません。何も言わずに、ただ働いているエリシャのそばを通る時に、自分の外套を彼の上に投げかけただけなのです。この出来事の前に、神からエリシャに何かの話があったのかどうかは、聖書に伝えられていませんが、この思いがけない突然の出来事に出遭った時、エリシャは牛を捨ててエリヤの後を追い、父母に別れの接吻をさせてくれるよう願って、「それからあなたに従います」と話しています。エリヤのなした風変わりな行為を神よりのものとして受け止め、正しく理解してすぐに対応する預言者的信仰のセンスが、エリシャの心の中に成熟していたしるしだと思います。エリヤもそれを認めて願いを許可しましたが、その時「私があなたに何をしたのか」という、不可解な言葉を口にします。よく判りませんが、これは、私があなたになした象徴的行為を忘れず、どんな思いがけない出来事の背後にも、神からの呼びかけを感知する信仰のセンスを大切にしているように、という意味を込めている言葉なのではないでしょうか。
③ 第二朗読には、キリストが「私たちを自由の身にして下さったのです。自由を得させるために」とありますが、ここで言われている「自由」とは、何からの自由なのでしょうか。この世の社会的身分制度や煩わしい外的労働、その他の生活の苦労からの自由ではありません。この朗読箇所に省かれているガラテヤ書5章2~12を読んでみますと、それは律法からの自由、すなわち律法の細かい規定を厳守することによって宗教的救いの恵みを得ようとする、ある意味では自分中心の利己的生き方からの自由を指していると思います。換言すれば、それは自分主導で何かを獲得しよう、所有しようとする欲求や生き方からの自由を指していると思います。したがって、最初に読まれる「奴隷のクビキに二度と繋がれてはなりません」という言葉は、そういう自分中心の生き方や肉の欲望に負けてはならないという意味だと思われます。
④ しかし、長年そういう生き方を続けて来て、その生き方がすっかり身についている通常の人間にとって、それはそう簡単なことではありません。ですからパウロは「だから、しっかりしなさい」と書いているのだと思います。仕事がうまく行かない時も、思わぬ困難や病気などに直面した時も、私たちの心を一番苦しめ悩ますのは、自分中心に自分主導で生きようとする私たち自身のエゴなのです。そのエゴからの自由を指しながら、パウロは、「あなた方は自由を得るために召し出されたのです」と書いているのではないでしょうか。では、どうしたら良いのでしょう。パウロはそれについて、「愛によって互いに仕えなさい」「隣人を自分のように愛しなさい」等々の勧めを挙げています。人に負けまい、少しでも人の上に立とうとして、「互いにかみ合い、共食い」しないように、とも警告しています。
⑤ 使徒パウロがここで私たちに言いたいのは、神の愛の霊に導かれて生きるようにせよ、ということだと思います。その愛の霊は、既に私たちの心の奥底に与えられているのです。何かの事で失敗して自力の限界を痛感させられ、心の上層部に居座っている古いエゴの殻が破られてしまった時、すなわち聖書に度々語られている「打ち砕かれた心」の状態になったような時、その時がチャンスです。心の奥底に現存しておられる神の霊に信仰と信頼の眼を向けるなら、その霊は私たちのその信仰に応えて働き出して下さいます。自分中心に何かを得ようとするのではなく、神中心に神の愛の霊に導かれて、この不信の闇の世に神の愛の灯を点そう、輝かそうとして生きること、神よりの恵みの保護や導きを人々に与え続けようとして生きること、それが、神が望んでおられる新約時代の信仰生活であり、古いエゴの悩ましい思い煩いから心を解放し、豊かな祝福と恵みを人々の上に呼び下す、幸せな生き方であると信じます。主キリストや聖母マリアのように、自分のためではなく、多くの人のために生きるよう心がけましょう。その時、天からの引力が私たちの心の中で働き、様々の善い成果を産み出してくれます。目には見えなくても、そういう引力は実際に働いているのです。人間中心の精神を捨てて神中心の心で生きようとする時に、その引力が心の中で働き始めるようです。
⑥ 本日の福音の始めにある「天に上げられる時期」という言葉は、主のご受難ご復活の時を指しています。主は既にそのことを弟子たちに予告して、エルサレムに向かう決意を固め、ガリラヤを後にされたのです。いわば死出の旅に出発し、その旅の途中に横たわるサマリア人の村で泊めてもらおうとしたのです。しかし、エルサレムのユダヤ人たちと敵対関係にあったサマリア人たちは、主の一行がエルサレムへ行こうとしているのを知って、宿泊を拒みました。使徒のヤコブとヨハネはそれを見て怒りましたが、主は二人を戒めて、一行は別の村へと向かいました。主は殺されるために、エルサレムへ向かっておられるのです。何か緊迫した雰囲気が一行の上に漂っているような、そんな状況での出来事だと思います。
⑦ しばらく行くと、次々と三人の人が登場しますが、ルカがここで登場させている人は、マタイ8章の平行記事では「弟子」と明記されていますし、エルサレムへと急いでおられた主に話しかけたのは、いずれも一行の後を追って来た弟子であったと思われます。数多くの大きな奇跡をなされた主イエスが、その主を殺害しようとしているユダヤ教指導者たちの本拠エルサレムに向かっておられると聞いて、メシアの支配する新しい時代が始まるのだと考え、この機会にメシアのために手柄を立てて、出世したいと望んで駆けつけたのかも知れません。最初の人は「どこへでも従って参ります」と申し上げていますが、主は、メシアに敵対する悪霊たちが策動する大きな過渡期には、どんな苦労をも厭わぬ覚悟が必要であることを諭すためなのか、「人の子には枕する所もない」などと話されました。
⑧ 第二の人は「私に従いなさい」という主からの呼びかけに、「まず父を葬りに行かせて下さい」と答えましたが、主はその弟子に「死んでいる者たちに、自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って、神の国を宣べ伝えなさい」という驚く程厳しい返事をなさいました。死に逝く父の世話や埋葬が、ユダヤ社会では息子にとって重大な義務であることを知ってのお言葉だと思います。その弟子は、主はエルサレムで敵対勢力を打ち破るか、殺されるかのどちらかであろうと考え、もし主が勝利して王位に登られたら、自分が逃げて弟子でなくなったのではなく、末期の父の世話と埋葬のため、主の許可を得て家に戻っていたのだということにしておけば、将来の出世の道が閉ざされることはないであろう、などと両天秤にかけて考えていたのかも知れません。それで主は、捨て身になって主に従おうとしていないその弟子の心を目覚めさせるために、厳しい言葉を話されたのかも知れません。「死んでいる者たちに」とあるのは、この世の人間関係や生活の配慮に没頭していて、まだ神の国の命に生きていない者たちという意味だと思います。
⑨ 第三の人は、「まず家族に暇乞いをしに行かせて下さい」と願いますが、主はその人にも、「鋤に手をかけてから後ろを振り返る者は、神の国に相応しくない」と冷たい返事をなさいます。本日の第一朗読では、エリヤがエリシャの願った家族への暇乞いをすぐに許可しましたが、主はここではそれを認めようとなさいません。その人の心が、まだこの世の人間関係などへの拘りを捨て切れずいるからなのかも知れません。私たちの心は本当に自分を捨て、聖母マリアのように神の僕・婢として主に従おうとしているでしょうか。心は無意識界ですので目に見えず自覚も難しいですが、日ごろの何気ない態度や言葉などに反映されることの多い自分の心をしっかりと吟味しながら、まだ何が自分に不足しているのかを見定め、神の導きと恵みを願い求めつつ、決心を新たに堅めましょう。
① 本日の三つの朗読箇所に共通しているのは、主に従う者が身につけるべき特性と言ってよいかも知れません。第一朗読にはそれが明確には示されていませんが、少し自由な推察を働かせながら探ってみましょう。第一朗読は預言者エリシャの召命の話ですが、その頃神の預言者は、王妃イゼベルに命を狙われて神の山ホレブ(すなわちシナイ山) に逃れたエリヤ一人だけでした。しかし、その預言者エリヤが天に召される日も近づいていました。そこで神はエリヤに現われて、神の山からダマスコの荒れ野へと向かわせ、二人の男に油を注いでそれぞれアラムの王、イスラエルの王となし、エリシャにも油を注いで、エリヤの後を継ぐ預言者にすることを命じます。こうしてアラムでもイスラエルでも軍事的対立が始まって、預言者の活躍を必要とする舞台が生まれたのでした。
② 第一朗読は、エリヤがそのエリシャを預言者として召し出す独特の仕方について伝えています。言葉で呼びかけて自分に従わせたのではありません。何も言わずに、ただ働いているエリシャのそばを通る時に、自分の外套を彼の上に投げかけただけなのです。この出来事の前に、神からエリシャに何かの話があったのかどうかは、聖書に伝えられていませんが、この思いがけない突然の出来事に出遭った時、エリシャは牛を捨ててエリヤの後を追い、父母に別れの接吻をさせてくれるよう願って、「それからあなたに従います」と話しています。エリヤのなした風変わりな行為を神よりのものとして受け止め、正しく理解してすぐに対応する預言者的信仰のセンスが、エリシャの心の中に成熟していたしるしだと思います。エリヤもそれを認めて願いを許可しましたが、その時「私があなたに何をしたのか」という、不可解な言葉を口にします。よく判りませんが、これは、私があなたになした象徴的行為を忘れず、どんな思いがけない出来事の背後にも、神からの呼びかけを感知する信仰のセンスを大切にしているように、という意味を込めている言葉なのではないでしょうか。
③ 第二朗読には、キリストが「私たちを自由の身にして下さったのです。自由を得させるために」とありますが、ここで言われている「自由」とは、何からの自由なのでしょうか。この世の社会的身分制度や煩わしい外的労働、その他の生活の苦労からの自由ではありません。この朗読箇所に省かれているガラテヤ書5章2~12を読んでみますと、それは律法からの自由、すなわち律法の細かい規定を厳守することによって宗教的救いの恵みを得ようとする、ある意味では自分中心の利己的生き方からの自由を指していると思います。換言すれば、それは自分主導で何かを獲得しよう、所有しようとする欲求や生き方からの自由を指していると思います。したがって、最初に読まれる「奴隷のクビキに二度と繋がれてはなりません」という言葉は、そういう自分中心の生き方や肉の欲望に負けてはならないという意味だと思われます。
④ しかし、長年そういう生き方を続けて来て、その生き方がすっかり身についている通常の人間にとって、それはそう簡単なことではありません。ですからパウロは「だから、しっかりしなさい」と書いているのだと思います。仕事がうまく行かない時も、思わぬ困難や病気などに直面した時も、私たちの心を一番苦しめ悩ますのは、自分中心に自分主導で生きようとする私たち自身のエゴなのです。そのエゴからの自由を指しながら、パウロは、「あなた方は自由を得るために召し出されたのです」と書いているのではないでしょうか。では、どうしたら良いのでしょう。パウロはそれについて、「愛によって互いに仕えなさい」「隣人を自分のように愛しなさい」等々の勧めを挙げています。人に負けまい、少しでも人の上に立とうとして、「互いにかみ合い、共食い」しないように、とも警告しています。
⑤ 使徒パウロがここで私たちに言いたいのは、神の愛の霊に導かれて生きるようにせよ、ということだと思います。その愛の霊は、既に私たちの心の奥底に与えられているのです。何かの事で失敗して自力の限界を痛感させられ、心の上層部に居座っている古いエゴの殻が破られてしまった時、すなわち聖書に度々語られている「打ち砕かれた心」の状態になったような時、その時がチャンスです。心の奥底に現存しておられる神の霊に信仰と信頼の眼を向けるなら、その霊は私たちのその信仰に応えて働き出して下さいます。自分中心に何かを得ようとするのではなく、神中心に神の愛の霊に導かれて、この不信の闇の世に神の愛の灯を点そう、輝かそうとして生きること、神よりの恵みの保護や導きを人々に与え続けようとして生きること、それが、神が望んでおられる新約時代の信仰生活であり、古いエゴの悩ましい思い煩いから心を解放し、豊かな祝福と恵みを人々の上に呼び下す、幸せな生き方であると信じます。主キリストや聖母マリアのように、自分のためではなく、多くの人のために生きるよう心がけましょう。その時、天からの引力が私たちの心の中で働き、様々の善い成果を産み出してくれます。目には見えなくても、そういう引力は実際に働いているのです。人間中心の精神を捨てて神中心の心で生きようとする時に、その引力が心の中で働き始めるようです。
⑥ 本日の福音の始めにある「天に上げられる時期」という言葉は、主のご受難ご復活の時を指しています。主は既にそのことを弟子たちに予告して、エルサレムに向かう決意を固め、ガリラヤを後にされたのです。いわば死出の旅に出発し、その旅の途中に横たわるサマリア人の村で泊めてもらおうとしたのです。しかし、エルサレムのユダヤ人たちと敵対関係にあったサマリア人たちは、主の一行がエルサレムへ行こうとしているのを知って、宿泊を拒みました。使徒のヤコブとヨハネはそれを見て怒りましたが、主は二人を戒めて、一行は別の村へと向かいました。主は殺されるために、エルサレムへ向かっておられるのです。何か緊迫した雰囲気が一行の上に漂っているような、そんな状況での出来事だと思います。
⑦ しばらく行くと、次々と三人の人が登場しますが、ルカがここで登場させている人は、マタイ8章の平行記事では「弟子」と明記されていますし、エルサレムへと急いでおられた主に話しかけたのは、いずれも一行の後を追って来た弟子であったと思われます。数多くの大きな奇跡をなされた主イエスが、その主を殺害しようとしているユダヤ教指導者たちの本拠エルサレムに向かっておられると聞いて、メシアの支配する新しい時代が始まるのだと考え、この機会にメシアのために手柄を立てて、出世したいと望んで駆けつけたのかも知れません。最初の人は「どこへでも従って参ります」と申し上げていますが、主は、メシアに敵対する悪霊たちが策動する大きな過渡期には、どんな苦労をも厭わぬ覚悟が必要であることを諭すためなのか、「人の子には枕する所もない」などと話されました。
⑧ 第二の人は「私に従いなさい」という主からの呼びかけに、「まず父を葬りに行かせて下さい」と答えましたが、主はその弟子に「死んでいる者たちに、自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って、神の国を宣べ伝えなさい」という驚く程厳しい返事をなさいました。死に逝く父の世話や埋葬が、ユダヤ社会では息子にとって重大な義務であることを知ってのお言葉だと思います。その弟子は、主はエルサレムで敵対勢力を打ち破るか、殺されるかのどちらかであろうと考え、もし主が勝利して王位に登られたら、自分が逃げて弟子でなくなったのではなく、末期の父の世話と埋葬のため、主の許可を得て家に戻っていたのだということにしておけば、将来の出世の道が閉ざされることはないであろう、などと両天秤にかけて考えていたのかも知れません。それで主は、捨て身になって主に従おうとしていないその弟子の心を目覚めさせるために、厳しい言葉を話されたのかも知れません。「死んでいる者たちに」とあるのは、この世の人間関係や生活の配慮に没頭していて、まだ神の国の命に生きていない者たちという意味だと思います。
⑨ 第三の人は、「まず家族に暇乞いをしに行かせて下さい」と願いますが、主はその人にも、「鋤に手をかけてから後ろを振り返る者は、神の国に相応しくない」と冷たい返事をなさいます。本日の第一朗読では、エリヤがエリシャの願った家族への暇乞いをすぐに許可しましたが、主はここではそれを認めようとなさいません。その人の心が、まだこの世の人間関係などへの拘りを捨て切れずいるからなのかも知れません。私たちの心は本当に自分を捨て、聖母マリアのように神の僕・婢として主に従おうとしているでしょうか。心は無意識界ですので目に見えず自覚も難しいですが、日ごろの何気ない態度や言葉などに反映されることの多い自分の心をしっかりと吟味しながら、まだ何が自分に不足しているのかを見定め、神の導きと恵みを願い求めつつ、決心を新たに堅めましょう。
2010年6月20日日曜日
説教集C年: 2007年6月24日 (日)、第12主日、洗礼者聖ヨハネの誕生(三ケ日)
朗読聖書: Ⅰ. イザヤ 49: 1~6. Ⅱ. 使徒 13: 22~26.
Ⅲ. ルカ福音書 1: 57~66, 80.
① 本日の第一朗読の出典である第二イザヤ書 (イザヤ40~55章) には、「主の僕の歌」と言われている歌が四つありますが、本日の朗読箇所はその第二番目の歌であります。イザヤ42章の1~7節に読まれる最初の歌は、「見よ、私の僕、私が支える者を」という言葉で始まって、神の霊を受け、叫ばず呼ばわらずに、裁きを導き出して確かなものとしつつ人々に教え、囚われ人を解放し、闇に住む人をその牢獄から救い出すために、主である神が形づくり、諸国の光として立てるという、言わば主の僕の召命について述べている、神ご自身の歌であります。
② それに比べますと、本日ここで朗読された第二の歌は、内容的にはほぼ同様に主の僕の召命と使命について述べており、3節と6節に神がその僕に語られたお言葉が引用されていますが、全体としては主の僕が話している歌であります。ついでに申しますと、イザヤ50章4~9節の第三の歌は、自分の受ける迫害について述べている主の僕の歌であり、52章13節から53章12節までの一番長い第四の歌は、同じく主の僕が受ける受難死についての歌ですが、始めの3節で神が語られた後、53章に入るとその受難死を目撃する「私たち」が主語となっていますから、救いの恵みを受けるに到る人類の歌と称してもよいでしょう。しかし、最後の2節に再び神が登場し、その受難死によって神の僕が多くの人を義人とし、夥しい人を戦利品として受けることを詠っています。
③ 神の僕メシアについての預言である第二の「主の僕の歌」を、カトリック教会が洗礼者ヨハネの誕生を祝うミサ聖祭の中で朗読するのは、天使ガブリエルによるヨハネ誕生の予告からヨハネ殉教までのその生涯を、メシアの生涯の先駆と受け止めているからだと思います。私たちも洗礼者ヨハネを、神においてメシアと内的に深く結ばれていた先駆者として崇め、ヨハネの説いた悔い改めの恵みを、その取次ぎによって豊かに受けるよう努めましょう。
④ 第二朗読は、使徒パウロが第一回伝道旅行の時、ピシデアのアンティオキアで、安息日にユダヤ教の会堂でなした長い説教の一部であります。イスラエルの民の長い歴史を通して度々民に語りかけ、民を守り導いて下さった神は、約束された救い主によって救いの御業が実現する直前に、洗礼者ヨハネにイスラエルの民全体に悔い改めの洗礼を宣べ伝えさせました。ヨハネは、自分が数百年来かみから約束されている偉大なメシアの先駆者であることを自覚して、本日の朗読箇所にもあるように、「私はその足の履物をお脱がせする値打ちもない」と、公然と人々に話していました。私たちも洗礼者ヨハネの模範に倣い、自分を神の僕・婢、神から今の世に派遣されている使者と考えて、ミサ聖祭毎に実際にこの祭壇に来臨して下さる救い主に対し、謙虚な畏れと信仰を表明するよう心がけたいものであります。
⑤ 本日の福音は、エリザベトから生まれた洗礼者ヨハネが、誕生日から八日目に割礼を受けた時の話ですが、「近所の人々や親類は、主がエリザベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った」という言葉や、「皆驚いた」、「近所の人々は皆恐れを感じた」などの言葉から推察すると、その割礼式の日が来るまで、近所の人々も親類の人たちも、老婦人エリザベトの奇跡的懐妊のことや男の子出産のことを全く知らずにいたのではないでしょうか。そこで、ルカ福音書の中で十分に詳述されていない洗礼者ヨハネの誕生にまつわる様々の異常事について、多少自由な想像を加えながらまとめて考察してみましょう。
⑥ この割礼式の十ヶ月ほど前に、アビアの組に属する老祭司ザカリアはエルサレム神殿で奉仕していました。アビアの組は、ダビデ王が制定したレビ族祭司24組のうちの第8組で、各組は一週間ずつ当番制で神殿に奉仕していました。神殿の収入は本来レビ族の祭司全員にバランスよく分配される筈のものでしたが、ハスモン家の大祭司が前2世紀の中葉にユダヤの政治権力を掌握してからの旧約末期には、その大祭司と結託しているサドカイ派の祭司たちが、神殿収入の大部分を自分たちのものにして祭司貴族のようになり、それ以外の祭司たちは年に2回一週間ずつ神殿に奉仕する報酬として支給される収入だけで生活する、貧しい下級祭司にされてしまいました。年に二週間の神殿奉仕の収入だけでは、長年住み慣れたエルサレムでは生活できません。それで多くの下級祭司は、エリコ周辺の誰の所有地でもない荒れ野や、ユダヤ南部の山地や荒れ野などの無住地に移住して開墾に励み、細々と生計を立てていました。当時の貧しい下級祭司たちが、神殿奉仕の二週間以外の時は都から遠く離れた不便な地域に生活していたのはそのためでした。この貧しいレビ族出身者の一部は、預言者的信仰精神の高揚に励みつつ、クムランやその他の諸所で共同生活を営んでいて、「エッセネ派」と呼ばれていますが、死期を間近にしていたザカリアとエリザベトも、幼子ヨハネの養育をそのエッセネ派の人たちに委ねてあの世に旅立ったようです。本日の福音の最後に、「幼子は、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた」とあるのは、そのことを指していると思います。察するに、洗礼者ヨハネはエッセネ派の教育を受けて成長し、そこで行われていた水のこ洗礼式を既に始まったメシア時代のために一般化して、悔い改める全ての人に授けたのではないでしょうか。
⑦ 神殿に奉仕する下級祭司たちは、毎日くじで選ばれた一人が神殿の聖所に香をたく勤めをしていました。サドカイ派に所属しない下級祭司にとってこの勤めは特別の名誉でしたので、できるだけ多くの祭司にこの名誉を与えるため、一度この勤めを果たした祭司は、その後は一生くじ引きから除外されていました。各祭司には年に14回もくじ引きの機会が与えられているのですから、祭司たちは早ければ30歳頃に、遅くとも40歳代、50歳代でほとんど皆聖所で香をたく勤めを果たしていたと思われます。しかし察するに、ザカリアは60歳代になってもくじに当たらず、神殿勤務の期間中は毎日、年若い祭司たちに伍してくじを引かなければなりませんでした。それは年老いたザカリアにとって耐え難い程の恥さらしであったと思われます。加えて、妻エリザベトに子供が授からないのは何か隠れた罪があるからではないか、というのが当時の人たちの一般的受け止め方でしたから、二人は神にその隠れた罪の赦しを願い求めて、ルカも書いているように、「主の全ての掟と規定とを落ち度なく踏み行う」ことに、他の人たちの何倍も細かく注意しながら努力していたと思います。
⑧ ところが、ある日そのザカリアにくじが当たったので、彼は老祭司の荘重さを保ちつつ、香炉と香をもって主の聖所に入って行きました。外では同僚の祭司たちと民衆が祈っていました。香をたいた時、彼は香壇の右に立つ天使を見て心乱れ、恐怖に襲われました。「恐れるな、ザカリア。お前の願い事は聞き入れられた」と、天使はエリザベトが男の子を産むことと、その子につける名前、その子が神から受ける恵みや使命などについて告げると、恐怖と緊張で心が固くなっていたザカリアは、「私は何によってそのこと(が本当だと) 知ることができましょうか。私は 老人で妻も年老いています」と、天使に答えました。すると天使は、「私は神の御前に立つガブリエルである。あなたにこの福音を伝えるために遣わされた。聞け、あなたはこれらの事が起こる日まで口が利けず、ものが言えなくなるであろう。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである」と告げ、ザカリアは直ちにオシとなり、生まれて来る男の子に天使から告げられたヨハネの名をつけるまで、ものを言うことができなくなりました。誤解しないように申しますが、長年細心の注意を払って信仰生活を営んで来たザカリアが、急に神の存在や全能の権威などを信じなくなったのではありません。自分と妻エリザベトに対する神の特別の愛が、信じられなかったのだと思います。これまでの数十年間、どれ程熱心に祈っても償いの業に励んでも、子供が生まれずくじ運も悪かったのですから、自分たちは隠れた罪を背負って神から退けられているのだと、信じ切っていたのだと思われます。
⑨ 外でザカリアを待っていた人たちは、非常に遅れて聖所から出て来た彼が口が利けず、身振りで説明するのを見て、彼が聖所内で幻を見たのだと分り、隠れた大きな罪を持つ身で聖所に入ったために、天罰を受けたのだと考えたことでしょう。勤めの期間が終わって家に帰る時のザカリアは、外的には大きな社会的恥に覆われていたと思います。しかし内的には、心がこれまでの掟中心の生き方から自分に対する神の愛とご計画中心の生き方へとゆっくりと大きく転向し、新しい希望のうちに家に帰り、そのことを妻エリザベトに筆記で伝えたことでしょう。民の宗教的伝統を堅持し、民を代表して祈ることを本務としていたレビ族では女性も文盲ではなく、エリザベトも聖母マリアも字を読み書きできたと思います。旧約の信仰生活から新約の信仰生活への転向は、「悔い改め」の説教者ヨハネが母の胎に孕まれる前に、既にその両親の心の中で始まっていたと考えられます。ギリシャ語のメタノイア (悔い改め) は、単に何かの悪い生活態度や悪習を改善することではなく、奥底の心の根本的考え方や生き方を転換することを意味していますが、それを短期間に実現させるためには、ダマスコでのサウロの改心の時のように、何か奥底の心を揺り動かすような苦い体験が必要だと思います。神はザカリアたちにも、その体験をさせたのだと思います。
⑩ 事によると、ザカリアが天罰を受けたという噂がレビ族の間に広まり、人々はその隠れた恐ろしい罪に汚染されないよう、オシとなったザカリアの家には近づかないようにしていたかも知れません。口の利けない老ザカリアも人々に弁明することなく、家に引きこもっていたことでしょう。しかし、エリザベトが懐妊すると、二人の心には全く新しい希望と旧約聖書理解が育ち始めたと思われます。そのことは、ヨハネに名前をつけて口が利けるようになった時のザカリアの讃歌に、雄弁に反映しています。懐妊したエリザベトは、ルカ福音1: 24によると、「五ヶ月の間引きこもった」とありますが、身重と老齢のため、山里の坂道を自由に歩けなくなったのかも知れません。そのため、同じ山里に住む村人たちは、エリザベトの懐妊を知らずにいたのだと思います。
⑪ しかし、よくしたことに、そこへ天使のお告げを受けた親戚の聖母マリアが訪ねて来て一緒に生活し、老夫婦の生活の世話をしてくれました。マリアの世話を受けてエリザベトが出産した時も、近隣の人たちは知らずにいたでしょうが、その割礼式のためにマリアがその人たちを呼び集めた時、初めて大きな喜びが皆を満たしたのだと思います。そして更に、口の利けなくなっていたザカリアが、神からのお告げに従って、親類にはないヨハネの名前を幼子につけた時、舌がほどけて神に対する讃歌を詠い、その中で幼子が神から与えられた使命についても語るのを聞いて、人々は神の新しい救いの御業に畏れや希望の念を抱くにいたり、それがユダヤの山里で話題になったのだと思います。洗礼者ヨハネの誕生を記念し感謝するミサ聖祭を献げるに当たり、私たちも、外的画一的な規則順守中心の旧約時代とは違う、神の新しい愛の働きと導きに対する預言者的センスや価値観を大切にするよう、決意を新たにして恵みを願うよう心がけましょう。
Ⅲ. ルカ福音書 1: 57~66, 80.
① 本日の第一朗読の出典である第二イザヤ書 (イザヤ40~55章) には、「主の僕の歌」と言われている歌が四つありますが、本日の朗読箇所はその第二番目の歌であります。イザヤ42章の1~7節に読まれる最初の歌は、「見よ、私の僕、私が支える者を」という言葉で始まって、神の霊を受け、叫ばず呼ばわらずに、裁きを導き出して確かなものとしつつ人々に教え、囚われ人を解放し、闇に住む人をその牢獄から救い出すために、主である神が形づくり、諸国の光として立てるという、言わば主の僕の召命について述べている、神ご自身の歌であります。
② それに比べますと、本日ここで朗読された第二の歌は、内容的にはほぼ同様に主の僕の召命と使命について述べており、3節と6節に神がその僕に語られたお言葉が引用されていますが、全体としては主の僕が話している歌であります。ついでに申しますと、イザヤ50章4~9節の第三の歌は、自分の受ける迫害について述べている主の僕の歌であり、52章13節から53章12節までの一番長い第四の歌は、同じく主の僕が受ける受難死についての歌ですが、始めの3節で神が語られた後、53章に入るとその受難死を目撃する「私たち」が主語となっていますから、救いの恵みを受けるに到る人類の歌と称してもよいでしょう。しかし、最後の2節に再び神が登場し、その受難死によって神の僕が多くの人を義人とし、夥しい人を戦利品として受けることを詠っています。
③ 神の僕メシアについての預言である第二の「主の僕の歌」を、カトリック教会が洗礼者ヨハネの誕生を祝うミサ聖祭の中で朗読するのは、天使ガブリエルによるヨハネ誕生の予告からヨハネ殉教までのその生涯を、メシアの生涯の先駆と受け止めているからだと思います。私たちも洗礼者ヨハネを、神においてメシアと内的に深く結ばれていた先駆者として崇め、ヨハネの説いた悔い改めの恵みを、その取次ぎによって豊かに受けるよう努めましょう。
④ 第二朗読は、使徒パウロが第一回伝道旅行の時、ピシデアのアンティオキアで、安息日にユダヤ教の会堂でなした長い説教の一部であります。イスラエルの民の長い歴史を通して度々民に語りかけ、民を守り導いて下さった神は、約束された救い主によって救いの御業が実現する直前に、洗礼者ヨハネにイスラエルの民全体に悔い改めの洗礼を宣べ伝えさせました。ヨハネは、自分が数百年来かみから約束されている偉大なメシアの先駆者であることを自覚して、本日の朗読箇所にもあるように、「私はその足の履物をお脱がせする値打ちもない」と、公然と人々に話していました。私たちも洗礼者ヨハネの模範に倣い、自分を神の僕・婢、神から今の世に派遣されている使者と考えて、ミサ聖祭毎に実際にこの祭壇に来臨して下さる救い主に対し、謙虚な畏れと信仰を表明するよう心がけたいものであります。
⑤ 本日の福音は、エリザベトから生まれた洗礼者ヨハネが、誕生日から八日目に割礼を受けた時の話ですが、「近所の人々や親類は、主がエリザベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った」という言葉や、「皆驚いた」、「近所の人々は皆恐れを感じた」などの言葉から推察すると、その割礼式の日が来るまで、近所の人々も親類の人たちも、老婦人エリザベトの奇跡的懐妊のことや男の子出産のことを全く知らずにいたのではないでしょうか。そこで、ルカ福音書の中で十分に詳述されていない洗礼者ヨハネの誕生にまつわる様々の異常事について、多少自由な想像を加えながらまとめて考察してみましょう。
⑥ この割礼式の十ヶ月ほど前に、アビアの組に属する老祭司ザカリアはエルサレム神殿で奉仕していました。アビアの組は、ダビデ王が制定したレビ族祭司24組のうちの第8組で、各組は一週間ずつ当番制で神殿に奉仕していました。神殿の収入は本来レビ族の祭司全員にバランスよく分配される筈のものでしたが、ハスモン家の大祭司が前2世紀の中葉にユダヤの政治権力を掌握してからの旧約末期には、その大祭司と結託しているサドカイ派の祭司たちが、神殿収入の大部分を自分たちのものにして祭司貴族のようになり、それ以外の祭司たちは年に2回一週間ずつ神殿に奉仕する報酬として支給される収入だけで生活する、貧しい下級祭司にされてしまいました。年に二週間の神殿奉仕の収入だけでは、長年住み慣れたエルサレムでは生活できません。それで多くの下級祭司は、エリコ周辺の誰の所有地でもない荒れ野や、ユダヤ南部の山地や荒れ野などの無住地に移住して開墾に励み、細々と生計を立てていました。当時の貧しい下級祭司たちが、神殿奉仕の二週間以外の時は都から遠く離れた不便な地域に生活していたのはそのためでした。この貧しいレビ族出身者の一部は、預言者的信仰精神の高揚に励みつつ、クムランやその他の諸所で共同生活を営んでいて、「エッセネ派」と呼ばれていますが、死期を間近にしていたザカリアとエリザベトも、幼子ヨハネの養育をそのエッセネ派の人たちに委ねてあの世に旅立ったようです。本日の福音の最後に、「幼子は、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた」とあるのは、そのことを指していると思います。察するに、洗礼者ヨハネはエッセネ派の教育を受けて成長し、そこで行われていた水のこ洗礼式を既に始まったメシア時代のために一般化して、悔い改める全ての人に授けたのではないでしょうか。
⑦ 神殿に奉仕する下級祭司たちは、毎日くじで選ばれた一人が神殿の聖所に香をたく勤めをしていました。サドカイ派に所属しない下級祭司にとってこの勤めは特別の名誉でしたので、できるだけ多くの祭司にこの名誉を与えるため、一度この勤めを果たした祭司は、その後は一生くじ引きから除外されていました。各祭司には年に14回もくじ引きの機会が与えられているのですから、祭司たちは早ければ30歳頃に、遅くとも40歳代、50歳代でほとんど皆聖所で香をたく勤めを果たしていたと思われます。しかし察するに、ザカリアは60歳代になってもくじに当たらず、神殿勤務の期間中は毎日、年若い祭司たちに伍してくじを引かなければなりませんでした。それは年老いたザカリアにとって耐え難い程の恥さらしであったと思われます。加えて、妻エリザベトに子供が授からないのは何か隠れた罪があるからではないか、というのが当時の人たちの一般的受け止め方でしたから、二人は神にその隠れた罪の赦しを願い求めて、ルカも書いているように、「主の全ての掟と規定とを落ち度なく踏み行う」ことに、他の人たちの何倍も細かく注意しながら努力していたと思います。
⑧ ところが、ある日そのザカリアにくじが当たったので、彼は老祭司の荘重さを保ちつつ、香炉と香をもって主の聖所に入って行きました。外では同僚の祭司たちと民衆が祈っていました。香をたいた時、彼は香壇の右に立つ天使を見て心乱れ、恐怖に襲われました。「恐れるな、ザカリア。お前の願い事は聞き入れられた」と、天使はエリザベトが男の子を産むことと、その子につける名前、その子が神から受ける恵みや使命などについて告げると、恐怖と緊張で心が固くなっていたザカリアは、「私は何によってそのこと(が本当だと) 知ることができましょうか。私は 老人で妻も年老いています」と、天使に答えました。すると天使は、「私は神の御前に立つガブリエルである。あなたにこの福音を伝えるために遣わされた。聞け、あなたはこれらの事が起こる日まで口が利けず、ものが言えなくなるであろう。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである」と告げ、ザカリアは直ちにオシとなり、生まれて来る男の子に天使から告げられたヨハネの名をつけるまで、ものを言うことができなくなりました。誤解しないように申しますが、長年細心の注意を払って信仰生活を営んで来たザカリアが、急に神の存在や全能の権威などを信じなくなったのではありません。自分と妻エリザベトに対する神の特別の愛が、信じられなかったのだと思います。これまでの数十年間、どれ程熱心に祈っても償いの業に励んでも、子供が生まれずくじ運も悪かったのですから、自分たちは隠れた罪を背負って神から退けられているのだと、信じ切っていたのだと思われます。
⑨ 外でザカリアを待っていた人たちは、非常に遅れて聖所から出て来た彼が口が利けず、身振りで説明するのを見て、彼が聖所内で幻を見たのだと分り、隠れた大きな罪を持つ身で聖所に入ったために、天罰を受けたのだと考えたことでしょう。勤めの期間が終わって家に帰る時のザカリアは、外的には大きな社会的恥に覆われていたと思います。しかし内的には、心がこれまでの掟中心の生き方から自分に対する神の愛とご計画中心の生き方へとゆっくりと大きく転向し、新しい希望のうちに家に帰り、そのことを妻エリザベトに筆記で伝えたことでしょう。民の宗教的伝統を堅持し、民を代表して祈ることを本務としていたレビ族では女性も文盲ではなく、エリザベトも聖母マリアも字を読み書きできたと思います。旧約の信仰生活から新約の信仰生活への転向は、「悔い改め」の説教者ヨハネが母の胎に孕まれる前に、既にその両親の心の中で始まっていたと考えられます。ギリシャ語のメタノイア (悔い改め) は、単に何かの悪い生活態度や悪習を改善することではなく、奥底の心の根本的考え方や生き方を転換することを意味していますが、それを短期間に実現させるためには、ダマスコでのサウロの改心の時のように、何か奥底の心を揺り動かすような苦い体験が必要だと思います。神はザカリアたちにも、その体験をさせたのだと思います。
⑩ 事によると、ザカリアが天罰を受けたという噂がレビ族の間に広まり、人々はその隠れた恐ろしい罪に汚染されないよう、オシとなったザカリアの家には近づかないようにしていたかも知れません。口の利けない老ザカリアも人々に弁明することなく、家に引きこもっていたことでしょう。しかし、エリザベトが懐妊すると、二人の心には全く新しい希望と旧約聖書理解が育ち始めたと思われます。そのことは、ヨハネに名前をつけて口が利けるようになった時のザカリアの讃歌に、雄弁に反映しています。懐妊したエリザベトは、ルカ福音1: 24によると、「五ヶ月の間引きこもった」とありますが、身重と老齢のため、山里の坂道を自由に歩けなくなったのかも知れません。そのため、同じ山里に住む村人たちは、エリザベトの懐妊を知らずにいたのだと思います。
⑪ しかし、よくしたことに、そこへ天使のお告げを受けた親戚の聖母マリアが訪ねて来て一緒に生活し、老夫婦の生活の世話をしてくれました。マリアの世話を受けてエリザベトが出産した時も、近隣の人たちは知らずにいたでしょうが、その割礼式のためにマリアがその人たちを呼び集めた時、初めて大きな喜びが皆を満たしたのだと思います。そして更に、口の利けなくなっていたザカリアが、神からのお告げに従って、親類にはないヨハネの名前を幼子につけた時、舌がほどけて神に対する讃歌を詠い、その中で幼子が神から与えられた使命についても語るのを聞いて、人々は神の新しい救いの御業に畏れや希望の念を抱くにいたり、それがユダヤの山里で話題になったのだと思います。洗礼者ヨハネの誕生を記念し感謝するミサ聖祭を献げるに当たり、私たちも、外的画一的な規則順守中心の旧約時代とは違う、神の新しい愛の働きと導きに対する預言者的センスや価値観を大切にするよう、決意を新たにして恵みを願うよう心がけましょう。
2010年6月13日日曜日
説教集C年: 2007年6月17日 (日)、2007年間第11主日(三ケ日)
朗読聖書:Ⅰ. サムエル下 12: 7~10, 13. Ⅱ. ガラテヤ 2: 16, 19~21. Ⅲ. ルカ福音書 7: 36~56.
① 本日の第一朗読は紀元前千年頃の話で、カナンの地の先住民ヘト人の出身者である家臣ウリヤの妻を奪って子を身ごもらせたダビデ王が、その姦通罪の発覚を恐れてウリヤを戦場で死なせたという、もっと酷い二重の罪を犯したことを、預言者ナタンが主の名によって厳しく咎めた話であります。預言者はこの叱責に続いて、ダビデ王の家族の中から反逆者が出てもっと恐ろしい罪を公然と犯すという、耐え難い程の天罰も王に予告しています。
② しかし、王がナタンに「私は主に罪を犯した」と告白し、悔悟の心を表明すると、本日の朗読箇所にもあるように、ナタンは「その主があなたの罪を取り除かれる。あなたは死の罰を免れる」と、神からの赦しと慰めの言葉を告げます。私たちにとって、神からのこのような赦しと励ましの言葉は大切だと思います。エフュソ書の2: 3に述べられているように、私たちは原罪により神の「怒りの子」として神に背を向け、神以外の被造物を選び取り、それを自分の人生の中心として 生きようとする、いわば神に対する忘恩と反逆の強い傾きをもって生れ付いています。
③ 私たちの人間性を生まれながら歪めている、この利己的自己中心の傾きは心の奥底に深く隠れていて、自分の持って生まれた自然の力ではどんなに努力しても勝てません。神のため人のためと思って為した献身的善業にも、いつの間にか無意識の内に入ってきてしまうほど根深い、本性的罪の傾きなのですから。ダビデ王がなした程の大きな罪は犯さないとして、心を細かく吟味してみますと、私たちも日々数多くの小さな忘恩や怠りの罪を犯しており、神から無意識の内にそれなりの小さな罰や失敗・不運などの天罰を受けているのかも知れません。しかし、ダビデ王のように神の憐れみの御心にひたすら縋りつつ、罪を赦して下さる神の愛と力に生かされて生きようと努めるなら、私たちも晩年のダビデ王のように、憐れんで救う神の新たな働きを生き生きと体験するようになるのではないでしょうか。
④ 使徒パウロは本日の第二朗読の中で「人は律法の実行によってではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされる」と書いていますが、ここで「信仰」とあるのは、ハバクク書2章やローマ書1章その他に「義人は信仰によって生きる」とある言葉なども総合的に参照してみますと、「信仰の実践」と考えてよいと思います。パウロはその理由として、「律法の実行によっては、誰一人として義とされないからです」と述べていますが、この言葉の背後には、彼が若い時にキリストの教会を迫害したという、苦い体験があると思います。改心前の彼は、誰にも負けない程熱心に律法の全ての規定を順守しようとしていた律法学者だったと思います。しかし、復活なされた主キリスト御出現の恵みに出会い、その主から厳しく叱責された時、神と社会のためと思ってなしていた律法の厳守は、神の新しい救いの御業を妨げるものであったことを痛感させられたのでした。
⑤ 彼はその時から、人間が自力で研究し順守する律法中心の立場を捨てて、ひたすら神の新しい導き中心の立場に転向し、その信仰に生きて下さる復活なされたキリストの命に内面から生かされる、新しい信仰実践に励むようになりました。「キリストが私の内に生きておられるのです。云々」の言葉は、この新しい信仰体験に根ざした述懐であると思います。私たちも使徒パウロの模範に見習い、主キリストが新約の神の民から求めておられるこのような信仰実践を、しっかりと体得するよう心がけたいものであります。
⑥ しかしここで、「律法の実行によっては誰一人として義とされない」という使徒パウロの言葉を、あまりにも理知的原理主義的に誤解しないことにも気をつけましょう。熱心なユダヤ教徒は現代でも律法の規定を研究し順守することに励んでいますが、彼らはその敬虔な信仰生活にどれ程努めても義とされずに皆滅んでしまうという意味ではないと思います。元来律法はアブラハムの神信仰を民族の伝統として子孫に受け継がせ、メシアによる救いの御業の地盤を備える目的で神ご自身から与えられた善いものであります。旧約時代からのその伝統を現代に至るまで守り続け、神信仰に励んでいるユダヤ人たちの上には、主キリストによる救いの恵みが豊かに注がれていると信じます。彼らは律法の実行という過ぎ行く行為によってではなく、その行為を通して表明されている神信仰と神の大きな憐れみの故に、皆永遠の救いへと導かれていると信じましょう。2千年前のユダヤ教指導層の中には、宗教的伝統の権威や法規を重視するあまり、心が一種の原理主義に囚われてメシアを正しく理解できず、死刑へと追い詰めてしまった人たちもいましたが、その後2千年にわたって耐えて来た数々の苦難に学んだユダヤ人たちは、今日では神から新たな道へと導かれつつあるように感じています。
⑦ 本日の福音の中では、主イエスを食事にお招きしたファリサイ派のシモンと、その時イエスの足元に後ろから近づき、泣きながら主の御足を涙でぬらし、自分の髪の毛でぬぐい、接吻して香油を塗った罪深い女とが比較されていますが、44節から46節に読まれる主イエスの言葉を誤解しないように致しましょう。長旅で足が汚れている時は別として、普通に客を食事に招待したような時には、足を洗う水を差し出す必要はなかったし、日頃親しく交際している友でない客を接吻で迎える義務もありませんでした。シモンの応対には、取り立てて言う程の無礼はなかったと思われます。しかし、主があえてシモンの応対を口になされたのは、シモンの親切な招待よりも遥かに大きな愛を表明した罪の女の態度と行為を際立たせるためであったと思われます。事によると、シモンはイエスの預言者的能力や人柄を試すために、イエスを招待した食事の場に、その町の罪の女が来るよう取り計らったのかも知れません。主はそれをご承知の上でシモンの招待を受け、罪の女に救いの恵みをお与えになったのかも知れません。
⑧ しかし、聖書学者の雨宮慧神父はここで、47節前半に読まれる主のお言葉をどう受け止めるかに、一つの問題があることを指摘しています。ギリシャ語の原文では、その箇所は「私はあなたに言う。彼女の多くの罪は赦された。なぜなら彼女は多く愛したからである」となっています。雨宮神父はこの言葉を、「彼女は多く愛したがゆえに私はあなたに言える、彼女の多くの罪は赦された」という意味に取れば、多く愛したことから分るように、彼女の多くの罪は赦されてしまっているという意味になるが、その場合その後の48節に、主が女にあらためて、「あなたの罪は赦された」と言われた言葉へのつながりが少し悪くなると言います。47節の「罪は赦された」は、現在完了形の動詞でもあるからです。
⑨ しかし神父はもう一つ、47節前半の言葉を「私はあなたに言う、彼女は多く愛したから彼女の多くの罪は赦された」という意味にとり、愛することが罪の赦しを受ける条件と考えるなら、48節の赦しの言葉へのつながりはよくなるが、しかしこの場合も、40節から46節へのつながりが不自然になる、と迷っています。しかし、神父は最後に、「二者択一でなくても良いと思う。ルカ自身、どちらの解釈も可能になるよう意識して両義的に述べたと考えることもできる」、「救いと愛は相互的である。救いが愛を生むと同時に、愛が救いを生み出す。この相関関係に人を含み込むのが、イエスとの出会いである」などと書いています。私が神学生であった時にも、主のこの言葉をめぐって話題になっていることを聞いたことがありますが、雨宮神父のこの解説で結構だと思います。しかしこのことと関連して、規則違反などの外的な罪の赦しは、お詫びの言葉や外的償いなどによって与えられるとしても、心の奥底に隠れ潜む罪の赦しは、神の愛の火を心に点火し燃え上がらせる実践によってのみ、与えられるものであることを心に銘記していましょう。罪の女がその罪の赦しを受けたのも、主イエスに対する愛を可能な限りで表明した実践を通してだったのではないでしょうか。
① 本日の第一朗読は紀元前千年頃の話で、カナンの地の先住民ヘト人の出身者である家臣ウリヤの妻を奪って子を身ごもらせたダビデ王が、その姦通罪の発覚を恐れてウリヤを戦場で死なせたという、もっと酷い二重の罪を犯したことを、預言者ナタンが主の名によって厳しく咎めた話であります。預言者はこの叱責に続いて、ダビデ王の家族の中から反逆者が出てもっと恐ろしい罪を公然と犯すという、耐え難い程の天罰も王に予告しています。
② しかし、王がナタンに「私は主に罪を犯した」と告白し、悔悟の心を表明すると、本日の朗読箇所にもあるように、ナタンは「その主があなたの罪を取り除かれる。あなたは死の罰を免れる」と、神からの赦しと慰めの言葉を告げます。私たちにとって、神からのこのような赦しと励ましの言葉は大切だと思います。エフュソ書の2: 3に述べられているように、私たちは原罪により神の「怒りの子」として神に背を向け、神以外の被造物を選び取り、それを自分の人生の中心として 生きようとする、いわば神に対する忘恩と反逆の強い傾きをもって生れ付いています。
③ 私たちの人間性を生まれながら歪めている、この利己的自己中心の傾きは心の奥底に深く隠れていて、自分の持って生まれた自然の力ではどんなに努力しても勝てません。神のため人のためと思って為した献身的善業にも、いつの間にか無意識の内に入ってきてしまうほど根深い、本性的罪の傾きなのですから。ダビデ王がなした程の大きな罪は犯さないとして、心を細かく吟味してみますと、私たちも日々数多くの小さな忘恩や怠りの罪を犯しており、神から無意識の内にそれなりの小さな罰や失敗・不運などの天罰を受けているのかも知れません。しかし、ダビデ王のように神の憐れみの御心にひたすら縋りつつ、罪を赦して下さる神の愛と力に生かされて生きようと努めるなら、私たちも晩年のダビデ王のように、憐れんで救う神の新たな働きを生き生きと体験するようになるのではないでしょうか。
④ 使徒パウロは本日の第二朗読の中で「人は律法の実行によってではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされる」と書いていますが、ここで「信仰」とあるのは、ハバクク書2章やローマ書1章その他に「義人は信仰によって生きる」とある言葉なども総合的に参照してみますと、「信仰の実践」と考えてよいと思います。パウロはその理由として、「律法の実行によっては、誰一人として義とされないからです」と述べていますが、この言葉の背後には、彼が若い時にキリストの教会を迫害したという、苦い体験があると思います。改心前の彼は、誰にも負けない程熱心に律法の全ての規定を順守しようとしていた律法学者だったと思います。しかし、復活なされた主キリスト御出現の恵みに出会い、その主から厳しく叱責された時、神と社会のためと思ってなしていた律法の厳守は、神の新しい救いの御業を妨げるものであったことを痛感させられたのでした。
⑤ 彼はその時から、人間が自力で研究し順守する律法中心の立場を捨てて、ひたすら神の新しい導き中心の立場に転向し、その信仰に生きて下さる復活なされたキリストの命に内面から生かされる、新しい信仰実践に励むようになりました。「キリストが私の内に生きておられるのです。云々」の言葉は、この新しい信仰体験に根ざした述懐であると思います。私たちも使徒パウロの模範に見習い、主キリストが新約の神の民から求めておられるこのような信仰実践を、しっかりと体得するよう心がけたいものであります。
⑥ しかしここで、「律法の実行によっては誰一人として義とされない」という使徒パウロの言葉を、あまりにも理知的原理主義的に誤解しないことにも気をつけましょう。熱心なユダヤ教徒は現代でも律法の規定を研究し順守することに励んでいますが、彼らはその敬虔な信仰生活にどれ程努めても義とされずに皆滅んでしまうという意味ではないと思います。元来律法はアブラハムの神信仰を民族の伝統として子孫に受け継がせ、メシアによる救いの御業の地盤を備える目的で神ご自身から与えられた善いものであります。旧約時代からのその伝統を現代に至るまで守り続け、神信仰に励んでいるユダヤ人たちの上には、主キリストによる救いの恵みが豊かに注がれていると信じます。彼らは律法の実行という過ぎ行く行為によってではなく、その行為を通して表明されている神信仰と神の大きな憐れみの故に、皆永遠の救いへと導かれていると信じましょう。2千年前のユダヤ教指導層の中には、宗教的伝統の権威や法規を重視するあまり、心が一種の原理主義に囚われてメシアを正しく理解できず、死刑へと追い詰めてしまった人たちもいましたが、その後2千年にわたって耐えて来た数々の苦難に学んだユダヤ人たちは、今日では神から新たな道へと導かれつつあるように感じています。
⑦ 本日の福音の中では、主イエスを食事にお招きしたファリサイ派のシモンと、その時イエスの足元に後ろから近づき、泣きながら主の御足を涙でぬらし、自分の髪の毛でぬぐい、接吻して香油を塗った罪深い女とが比較されていますが、44節から46節に読まれる主イエスの言葉を誤解しないように致しましょう。長旅で足が汚れている時は別として、普通に客を食事に招待したような時には、足を洗う水を差し出す必要はなかったし、日頃親しく交際している友でない客を接吻で迎える義務もありませんでした。シモンの応対には、取り立てて言う程の無礼はなかったと思われます。しかし、主があえてシモンの応対を口になされたのは、シモンの親切な招待よりも遥かに大きな愛を表明した罪の女の態度と行為を際立たせるためであったと思われます。事によると、シモンはイエスの預言者的能力や人柄を試すために、イエスを招待した食事の場に、その町の罪の女が来るよう取り計らったのかも知れません。主はそれをご承知の上でシモンの招待を受け、罪の女に救いの恵みをお与えになったのかも知れません。
⑧ しかし、聖書学者の雨宮慧神父はここで、47節前半に読まれる主のお言葉をどう受け止めるかに、一つの問題があることを指摘しています。ギリシャ語の原文では、その箇所は「私はあなたに言う。彼女の多くの罪は赦された。なぜなら彼女は多く愛したからである」となっています。雨宮神父はこの言葉を、「彼女は多く愛したがゆえに私はあなたに言える、彼女の多くの罪は赦された」という意味に取れば、多く愛したことから分るように、彼女の多くの罪は赦されてしまっているという意味になるが、その場合その後の48節に、主が女にあらためて、「あなたの罪は赦された」と言われた言葉へのつながりが少し悪くなると言います。47節の「罪は赦された」は、現在完了形の動詞でもあるからです。
⑨ しかし神父はもう一つ、47節前半の言葉を「私はあなたに言う、彼女は多く愛したから彼女の多くの罪は赦された」という意味にとり、愛することが罪の赦しを受ける条件と考えるなら、48節の赦しの言葉へのつながりはよくなるが、しかしこの場合も、40節から46節へのつながりが不自然になる、と迷っています。しかし、神父は最後に、「二者択一でなくても良いと思う。ルカ自身、どちらの解釈も可能になるよう意識して両義的に述べたと考えることもできる」、「救いと愛は相互的である。救いが愛を生むと同時に、愛が救いを生み出す。この相関関係に人を含み込むのが、イエスとの出会いである」などと書いています。私が神学生であった時にも、主のこの言葉をめぐって話題になっていることを聞いたことがありますが、雨宮神父のこの解説で結構だと思います。しかしこのことと関連して、規則違反などの外的な罪の赦しは、お詫びの言葉や外的償いなどによって与えられるとしても、心の奥底に隠れ潜む罪の赦しは、神の愛の火を心に点火し燃え上がらせる実践によってのみ、与えられるものであることを心に銘記していましょう。罪の女がその罪の赦しを受けたのも、主イエスに対する愛を可能な限りで表明した実践を通してだったのではないでしょうか。
2010年6月6日日曜日
説教集C年: 2007年6月10日 (日)、キリストの聖体 (三ケ日)
朗読聖書: Ⅰ. 創世記 14: 18~20. Ⅱ. コリント前 11: 23~26.
Ⅲ. ルカ福音書 11b~17.
① 今年の2月22日、聖ペトロの聖座の祝日に、ローマ教皇は ”Sacramentum caritatis (愛の秘跡)”と題する使徒的勧告を発布しましたが、それは2005年のクリスマスに発布された現教皇の最初の回勅『神は愛』よりも長いもので、主の御聖体の秘跡とその神秘について詳しく説明しています。第一部、第二部、第三部と三つに分けて伝統的教義と典礼とその効用などについて詳述しており、特に主の御聖体の神秘を生きることについて、ヨハネ福音書、使徒パウロの書簡、アウグスティヌスや前教皇の言葉などを引用しながら述べている第三部には、熟読して学ぶべきことが多いと思います。いずれ日本語にも翻訳されて出版されるでしょうから、ここでは本日の朗読聖書から学ぶことにしたいと思います。
② 本日の第一朗読には、いと高き神の祭司であったサレムの王メルキゼデクのことが述べられています。聖書以外にはどこにも史料の残っていない、この王について少し考えてみましょう。彼は「天地の創り主、いと高き神」に仕える祭司ですから、アブラハムと同じ神を信奉しています。宇宙の創り主である神は、当時アブラムと称していたユダヤ人の先祖にだけ特別にご自身を啓示なされたのではなく、同じ時代に、恐らくはアブラムよりも前に、サレムの王メルキゼデクにも親しく語りかけ、この王を神の祭司としておられたようです。ここでサレムとある町は、詩篇76:3ではエルサレムと同一視されています。この王は、奇襲作戦によって敵軍から甥ロトの一家とその町の人々・財産などを奪回して来たアブラムの勝利を慶賀して、パンとぶどう酒を持参し、アブラムに神の祝福を与えたのです。感激したアブラムは、その全財産の十分の一をこの祭司を介して神に献げたようです。
③ 創世記に記されているこの出来事一つを見ても、神はユダヤ人以外の人々の中でも親しく働いておられ、しかもサレムの王は、アブラムよりも神に近い存在・祭司とされていることを、心に銘記していたいと思います。ダビデの詠った詩篇110: 4によると、神は将来この世に派遣なさるメシアについて「メルキゼデクのように、お前は永遠の祭司」と語っておられます。このメルキゼデクは、イスラエルのレビ族に所属する祭司ではありません。メシアもレビ族の祭司ではなく、初めもなく終りもなく、神によって直接に全人類のために立てられた祭司、メルキゼデクのように王であって祭司である方なのです。サレムの王という称号は、ヘブライ語では「平和の王」という意味ですが、メルキゼデクという名前も、ヘブライ語では「私の王は義」という意味になるそうです。これらの意味は、そのまま主キリストにも相応しいと思います。主がパンとぶどう酒による秘跡を人類にお与えになったことを記念し感謝する聖体の祭日に当たり、アブラムにパンとぶどう酒を介して神の祝福を与えた、遠い昔の祭司メルキゼデクの人類愛も、感謝のうちに合わせて記念致しましょう。
④ 本日の第二朗読の最後に読まれる、「あなた方は、このパンを食べこの杯から飲む毎に、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです」という使徒パウロの言葉も、大切だと思います。「主の死を告げ知らせる」というのは、単に口先で「主が死んだ」などと、人々に語り伝えることを指しているのではありません。パンは主のお体を、ぶどう酒は主の御血を指していますが、その二つを別々に祭壇上で神への供え物にするということは、主が受難死によってこの世の命には既に死に、救いの恵みを人類の上に呼び下すいけにえ、神への供え物になっておられること、いけにえとしてのお姿を天父に提示しつつ、今も私たちの上に恵みと祝福を呼び下しておられることを示していると思います。そしてその主のお体と御血を拝領して、自分の血となし肉となす私たち信仰者は、主の御精神、主の御力に内面から生かされ、新たな神の愛に生きる恵みを受けるのであることをも、示していると思います。主はそのためにこそこの世に死んで、ご自身を私たちの糧となされたのですから。
⑤ 「主の死を告げ知らせる」とは、時間空間を越えた絶対的存在であられる神とこの世の被造界とを赦しと愛の絆で結ぶに至った主のご受難が、時間空間を越えて今も私たちのうちに現存し、数々の恵みを齎してくださっているという深く隠れている霊的現実を自覚し、それに相応しい内的実を結ぶことにより、世の人々にその事実を実践的に証しすることを意味していると思います。聖体奉挙の時「信仰の神秘」という司祭の言葉に、会衆は「主の死を思い、復活をたたえよう。主が来られるまで」と唱えますが、その時私たちのこの信仰と決意を新たに致しましょう。古代のギリシャ教父たちは、この「信仰の神秘」という言葉を唱える時、聖バジリオの製作に基づく第四奉献文にもあるように、「今ここに」時間空間を越えて現存なされる主に対する信仰を新たにしたと聞いています。私たちもその古い伝統を大切に致しましょう。
⑥ 本日の福音にある、五つのパンと二匹の魚で男たち五千人もの群集を満腹させた奇跡は、四つの福音書全てに扱われている出来事であります。二つ、あるいは三つの福音書に扱われている出来事は少なくありませんが、四つの福音書に共通して読まれる出来事は、主のエルサレム入城とご受難・ご復活以外には、このパンの奇跡だけです。それを思うと、使徒たちと初代教会は、このパンの奇跡を特別に重視しながら、語り伝えていたのではないでしょうか。しかし、それぞれの福音書は、多少違った視点からこの出来事を描写しています。例えばマルコ福音書には、「大勢の群集が」「飼い主のいない羊のような有様なのを深く憐れんだ」主が、いろいろと教えた後に、彼らを「組に分けて青草の上に座らせ」てから、この奇跡をなされたように描かれており、これらの表現から察すると、主を無数の人々を豊かに養う牧者として提示しようとする意図が感じられます。それに比べると、本日の福音であるルカ福音書の描写にはこれらの言葉が読まれず、弟子たちにこの奇跡を体験させ考えさせようとしておられる主のお姿の方に、もっと眼を向けているように思われます。ルカは、この出来事のすぐ前に、主がなされた様々の奇跡的出来事のことを耳にした領主ヘロデが、イエズスは一体何者なのかと当惑していることを述べ、このパンの奇跡のすぐ後で、主が弟子たちに「人々は私を何者だと言っているのか」、「では、あなた方は私を何者だと言うのか」と尋ね、ペトロが「神からのメシアです」と信仰告白する話を載せていますから、弟子たちに主は一体何者と考えさせる観点から、このパンの奇跡を描写したのだと思われます。
⑦ そのルカによると、大勢の群集に対する主の説教や癒しの働きが長引き日が傾きかけたので、12人の弟子たちが群集の食べ物のことを心配し、「群集を解散させて下さい。云々」と主に願いました。それに対して主は、「あなた方が彼らに食べ物を与えなさい」とお命じになり、彼らはすぐ「私たちには、パン五つと魚二匹しかありません。云々」と答えました。すると主は、人々を50人位ずつ組にして座らせ、その五つのパンと二匹の魚とを取って祈りを捧げてから、それらを裂いて弟子たちに渡し、群衆に配らせました。それが既に日が傾いた日没近い時間帯のことであり、全ての人がパンと魚を食べて満腹し、食べ残したパン屑を集めて12の籠をいっぱいにした時間なども考慮に入れると、パンと魚は、主お一人の手元でだけ、裂く度毎に次々と増えたのではないと思われます。50人位ずつ百組にも分かれて座るとなると、かなり遠くに座っている人々も多いのですから、そこへ主の御許から大量のパンと魚を運ぶだけでも、多くの時間が失われることになり、まだ全員に行き渡らない内に日が沈んでしまうことでしょう。そこで私は、パンと魚は弟子たちの手元でも、群集に渡す度毎に増えたのではないかと考えます。奇跡をなす主の力が、遠く離れている弟子たちの中にも現存して、糧を必要としている無数の人をリアル・タイムで養うことができるということを、主はこの奇跡により弟子たちに体験させ、主が全能の神よりの人であることを実践的に証したのではないでしょうか。
⑧ その主は、時間的空間的にもっと遥かに遠く離れている現代の私たちにも、司祭の献げるミサ聖祭の中で聖別されたパンとぶどう酒という形で、大きな恵みの糧を与えて下さいます。本日は、主のその愛と現存に対する信仰を堅め、このご聖体の秘跡に感謝する祭日であります。パンとぶどう酒という、食べ物と飲み物の中にご自身の御命を入れて無数の信仰者を内面から養い、その人々を通してこの世に世の終わりまで現存し続けるという、真に驚嘆に値する奇跡は、全能の神なればこそできる愛の御業、愛の恵みであり、私たち人間の側からは全く理解も説明もし難い現実、ただ心の意志で謙虚に受け止め信じることしかできない真実であります。ヨハネ福音書6章後半によると、主もこの真理の前に多くの理知的人間が躓き離れ去ることは覚悟しておられたようですが、それでも敢えて、「人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方の内に命はない」「私の肉は真の食べ物、私の血は真の飲み物だからである」などと、人間理性を躓かすような言葉を幾度も断言しておられます。それまで主に従っていた弟子たちの多くは、この理解し難い言葉に躓いて主の御許から離れ去りました。しかし、主に心から信服していた使徒たちは、自分の頭で理解できなくても、主に信頼する心の意志で主の御許に留まり続け、後でそのお言葉の本当の意味を深く理解するに到りました。主は私たちからも、このような心の信頼、心の信仰を求めておられると思います。
⑨ 私は1969年の夏休みに高野山で三泊四日の研修を受けたのを初めとして、2000年まで31年間にわたってほとんど毎年のように、比叡山やその他諸宗派・諸宗教の本山や中心的拠点で二泊三日の研修を受けており、1980年代にはユダヤ教やイスラム教や東方正教会の所でも研修を受けましたが、神がご自身を人間の食べ物・飲み物となしてまで、これほど近く人類の中に現存し、内面から人類をまた宇宙世界全体を支え導いていて下さることを堅く信奉している宗教は、カトリックと東方正教会など、キリストの制定なされたミサ聖祭を堅持している宗教以外には、どこにも見られませんでした。その意味でも私は、まだミサ聖祭の偉大な価値を知らずにいる人類全体をも、この秘跡を通して豊かに祝福し、護り、支えておられる神に、私たちは全人類を代表して特別に感謝と賛美を捧げる責務があると痛感しています。日ごろの感謝の不足を反省し、本日はこれまで受けた数々のお恵みのためにも、主に心を込めて感謝致しましょう。
Ⅲ. ルカ福音書 11b~17.
① 今年の2月22日、聖ペトロの聖座の祝日に、ローマ教皇は ”Sacramentum caritatis (愛の秘跡)”と題する使徒的勧告を発布しましたが、それは2005年のクリスマスに発布された現教皇の最初の回勅『神は愛』よりも長いもので、主の御聖体の秘跡とその神秘について詳しく説明しています。第一部、第二部、第三部と三つに分けて伝統的教義と典礼とその効用などについて詳述しており、特に主の御聖体の神秘を生きることについて、ヨハネ福音書、使徒パウロの書簡、アウグスティヌスや前教皇の言葉などを引用しながら述べている第三部には、熟読して学ぶべきことが多いと思います。いずれ日本語にも翻訳されて出版されるでしょうから、ここでは本日の朗読聖書から学ぶことにしたいと思います。
② 本日の第一朗読には、いと高き神の祭司であったサレムの王メルキゼデクのことが述べられています。聖書以外にはどこにも史料の残っていない、この王について少し考えてみましょう。彼は「天地の創り主、いと高き神」に仕える祭司ですから、アブラハムと同じ神を信奉しています。宇宙の創り主である神は、当時アブラムと称していたユダヤ人の先祖にだけ特別にご自身を啓示なされたのではなく、同じ時代に、恐らくはアブラムよりも前に、サレムの王メルキゼデクにも親しく語りかけ、この王を神の祭司としておられたようです。ここでサレムとある町は、詩篇76:3ではエルサレムと同一視されています。この王は、奇襲作戦によって敵軍から甥ロトの一家とその町の人々・財産などを奪回して来たアブラムの勝利を慶賀して、パンとぶどう酒を持参し、アブラムに神の祝福を与えたのです。感激したアブラムは、その全財産の十分の一をこの祭司を介して神に献げたようです。
③ 創世記に記されているこの出来事一つを見ても、神はユダヤ人以外の人々の中でも親しく働いておられ、しかもサレムの王は、アブラムよりも神に近い存在・祭司とされていることを、心に銘記していたいと思います。ダビデの詠った詩篇110: 4によると、神は将来この世に派遣なさるメシアについて「メルキゼデクのように、お前は永遠の祭司」と語っておられます。このメルキゼデクは、イスラエルのレビ族に所属する祭司ではありません。メシアもレビ族の祭司ではなく、初めもなく終りもなく、神によって直接に全人類のために立てられた祭司、メルキゼデクのように王であって祭司である方なのです。サレムの王という称号は、ヘブライ語では「平和の王」という意味ですが、メルキゼデクという名前も、ヘブライ語では「私の王は義」という意味になるそうです。これらの意味は、そのまま主キリストにも相応しいと思います。主がパンとぶどう酒による秘跡を人類にお与えになったことを記念し感謝する聖体の祭日に当たり、アブラムにパンとぶどう酒を介して神の祝福を与えた、遠い昔の祭司メルキゼデクの人類愛も、感謝のうちに合わせて記念致しましょう。
④ 本日の第二朗読の最後に読まれる、「あなた方は、このパンを食べこの杯から飲む毎に、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです」という使徒パウロの言葉も、大切だと思います。「主の死を告げ知らせる」というのは、単に口先で「主が死んだ」などと、人々に語り伝えることを指しているのではありません。パンは主のお体を、ぶどう酒は主の御血を指していますが、その二つを別々に祭壇上で神への供え物にするということは、主が受難死によってこの世の命には既に死に、救いの恵みを人類の上に呼び下すいけにえ、神への供え物になっておられること、いけにえとしてのお姿を天父に提示しつつ、今も私たちの上に恵みと祝福を呼び下しておられることを示していると思います。そしてその主のお体と御血を拝領して、自分の血となし肉となす私たち信仰者は、主の御精神、主の御力に内面から生かされ、新たな神の愛に生きる恵みを受けるのであることをも、示していると思います。主はそのためにこそこの世に死んで、ご自身を私たちの糧となされたのですから。
⑤ 「主の死を告げ知らせる」とは、時間空間を越えた絶対的存在であられる神とこの世の被造界とを赦しと愛の絆で結ぶに至った主のご受難が、時間空間を越えて今も私たちのうちに現存し、数々の恵みを齎してくださっているという深く隠れている霊的現実を自覚し、それに相応しい内的実を結ぶことにより、世の人々にその事実を実践的に証しすることを意味していると思います。聖体奉挙の時「信仰の神秘」という司祭の言葉に、会衆は「主の死を思い、復活をたたえよう。主が来られるまで」と唱えますが、その時私たちのこの信仰と決意を新たに致しましょう。古代のギリシャ教父たちは、この「信仰の神秘」という言葉を唱える時、聖バジリオの製作に基づく第四奉献文にもあるように、「今ここに」時間空間を越えて現存なされる主に対する信仰を新たにしたと聞いています。私たちもその古い伝統を大切に致しましょう。
⑥ 本日の福音にある、五つのパンと二匹の魚で男たち五千人もの群集を満腹させた奇跡は、四つの福音書全てに扱われている出来事であります。二つ、あるいは三つの福音書に扱われている出来事は少なくありませんが、四つの福音書に共通して読まれる出来事は、主のエルサレム入城とご受難・ご復活以外には、このパンの奇跡だけです。それを思うと、使徒たちと初代教会は、このパンの奇跡を特別に重視しながら、語り伝えていたのではないでしょうか。しかし、それぞれの福音書は、多少違った視点からこの出来事を描写しています。例えばマルコ福音書には、「大勢の群集が」「飼い主のいない羊のような有様なのを深く憐れんだ」主が、いろいろと教えた後に、彼らを「組に分けて青草の上に座らせ」てから、この奇跡をなされたように描かれており、これらの表現から察すると、主を無数の人々を豊かに養う牧者として提示しようとする意図が感じられます。それに比べると、本日の福音であるルカ福音書の描写にはこれらの言葉が読まれず、弟子たちにこの奇跡を体験させ考えさせようとしておられる主のお姿の方に、もっと眼を向けているように思われます。ルカは、この出来事のすぐ前に、主がなされた様々の奇跡的出来事のことを耳にした領主ヘロデが、イエズスは一体何者なのかと当惑していることを述べ、このパンの奇跡のすぐ後で、主が弟子たちに「人々は私を何者だと言っているのか」、「では、あなた方は私を何者だと言うのか」と尋ね、ペトロが「神からのメシアです」と信仰告白する話を載せていますから、弟子たちに主は一体何者と考えさせる観点から、このパンの奇跡を描写したのだと思われます。
⑦ そのルカによると、大勢の群集に対する主の説教や癒しの働きが長引き日が傾きかけたので、12人の弟子たちが群集の食べ物のことを心配し、「群集を解散させて下さい。云々」と主に願いました。それに対して主は、「あなた方が彼らに食べ物を与えなさい」とお命じになり、彼らはすぐ「私たちには、パン五つと魚二匹しかありません。云々」と答えました。すると主は、人々を50人位ずつ組にして座らせ、その五つのパンと二匹の魚とを取って祈りを捧げてから、それらを裂いて弟子たちに渡し、群衆に配らせました。それが既に日が傾いた日没近い時間帯のことであり、全ての人がパンと魚を食べて満腹し、食べ残したパン屑を集めて12の籠をいっぱいにした時間なども考慮に入れると、パンと魚は、主お一人の手元でだけ、裂く度毎に次々と増えたのではないと思われます。50人位ずつ百組にも分かれて座るとなると、かなり遠くに座っている人々も多いのですから、そこへ主の御許から大量のパンと魚を運ぶだけでも、多くの時間が失われることになり、まだ全員に行き渡らない内に日が沈んでしまうことでしょう。そこで私は、パンと魚は弟子たちの手元でも、群集に渡す度毎に増えたのではないかと考えます。奇跡をなす主の力が、遠く離れている弟子たちの中にも現存して、糧を必要としている無数の人をリアル・タイムで養うことができるということを、主はこの奇跡により弟子たちに体験させ、主が全能の神よりの人であることを実践的に証したのではないでしょうか。
⑧ その主は、時間的空間的にもっと遥かに遠く離れている現代の私たちにも、司祭の献げるミサ聖祭の中で聖別されたパンとぶどう酒という形で、大きな恵みの糧を与えて下さいます。本日は、主のその愛と現存に対する信仰を堅め、このご聖体の秘跡に感謝する祭日であります。パンとぶどう酒という、食べ物と飲み物の中にご自身の御命を入れて無数の信仰者を内面から養い、その人々を通してこの世に世の終わりまで現存し続けるという、真に驚嘆に値する奇跡は、全能の神なればこそできる愛の御業、愛の恵みであり、私たち人間の側からは全く理解も説明もし難い現実、ただ心の意志で謙虚に受け止め信じることしかできない真実であります。ヨハネ福音書6章後半によると、主もこの真理の前に多くの理知的人間が躓き離れ去ることは覚悟しておられたようですが、それでも敢えて、「人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方の内に命はない」「私の肉は真の食べ物、私の血は真の飲み物だからである」などと、人間理性を躓かすような言葉を幾度も断言しておられます。それまで主に従っていた弟子たちの多くは、この理解し難い言葉に躓いて主の御許から離れ去りました。しかし、主に心から信服していた使徒たちは、自分の頭で理解できなくても、主に信頼する心の意志で主の御許に留まり続け、後でそのお言葉の本当の意味を深く理解するに到りました。主は私たちからも、このような心の信頼、心の信仰を求めておられると思います。
⑨ 私は1969年の夏休みに高野山で三泊四日の研修を受けたのを初めとして、2000年まで31年間にわたってほとんど毎年のように、比叡山やその他諸宗派・諸宗教の本山や中心的拠点で二泊三日の研修を受けており、1980年代にはユダヤ教やイスラム教や東方正教会の所でも研修を受けましたが、神がご自身を人間の食べ物・飲み物となしてまで、これほど近く人類の中に現存し、内面から人類をまた宇宙世界全体を支え導いていて下さることを堅く信奉している宗教は、カトリックと東方正教会など、キリストの制定なされたミサ聖祭を堅持している宗教以外には、どこにも見られませんでした。その意味でも私は、まだミサ聖祭の偉大な価値を知らずにいる人類全体をも、この秘跡を通して豊かに祝福し、護り、支えておられる神に、私たちは全人類を代表して特別に感謝と賛美を捧げる責務があると痛感しています。日ごろの感謝の不足を反省し、本日はこれまで受けた数々のお恵みのためにも、主に心を込めて感謝致しましょう。
登録:
投稿 (Atom)